- エフィカシーは、心理学で「自己効力感」と訳される言葉で、特定の事柄に対する自信のことです。
- エフィカシーが高い組織では、業績向上と生産性の大幅なアップが実現されます。
- コーチングは、エフィカシー向上において効果的な手法の一つです。
「部下のやる気が低い」「チームの成果が上がらない」。

そんな悩みに、どうアプローチすれば良いか迷っていませんか?
「エフィカシー」という言葉は知っていても、自己肯定感との違いや、具体的な高め方が分からず、導入をためらっている管理職の方も多いでしょう。
エフィカシーは、部下の意欲を引き出し、目標達成に向けた行動を促すための重要な心理的資源です。
つまり、チーム全体のモチベーションや生産性を高めるうえで、エフィカシーは欠かせない土台となるのです。
この記事を読めば、エフィカシーの本当の意味を理解し、チームの生産性を上げる鍵が見つかります。
「エフィカシーとは何か」という基本的な意味から、コーチングやアファメーションを用いた高め方、エフィカシーが高い人・低い人の特徴まで網羅的に解説します。
さらに、部下の意欲を高め、目標達成を後押しするマネジメント手法として、エフィカシーをどのように活用できるかも具体的に紹介します。



感覚的な言葉を、チームを動かすマネジメント資源に変え、部下が自律的に挑戦する組織づくりの第一歩を踏み出しましょう。
エフィカシーとは何か?その意味と背景を知る


「最近よく聞く『エフィカシー』って、一体なんだろう?」「自己肯定感とどう違うの?」チームの成果を上げたいと願うリーダーや管理職の方なら、一度はそう思ったことがあるかもしれません。
この章では、そんな疑問を解消するために、エフィカシーの基本的な意味から、混同されがちな自己肯定感との違い、そしてコーチングへの応用まで、基礎から分かりやすく解説します。
- 心理学における正確な定義と英語での意味
- 自己肯定感との根本的な違いと使い分け方
- 苫米地英人氏による独自のエフィカシー理論とコーチング応用
エフィカシーの意味と英語での定義
エフィカシー(efficacy)とは、心理学で「自己効力感」と訳される言葉で、平たく言えば「この課題・この状況なら、自分はうまくやれるはずだ!」という、特定の事柄に対する自信のことです。
カナダの心理学者アルバート・バンデューラが提唱した考え方で、個人の行動を左右する重要な要素とされています。
英語の「efficacy」が「効力・有効性」を意味することからもわかるように、これは単なる気合や精神論ではありません。
変化が激しく先が見えない現代(VUCA時代)において、組織や個人のパフォーマンスを左右するカギとして、今あらためて注目されているのです。
例えば、営業職であれば「新規顧客への提案で成約を取れる」、管理職であれば「困難なプロジェクトをチームで成功させられる」といった具体的な課題に対する自信がエフィカシーです。
自己肯定感との決定的な違い
エフィカシーと自己肯定感は、どちらも「自信」に関わる言葉ですが、その向かう先が全く異なります。
一番の違いは、エフィカシーが「未来の行動」に対する自信であるのに対し、自己肯定感は「過去や現在のありのままの自分」を認める感覚である、という点です。
自己肯定感(セルフエスティーム)は、成功や失敗といった結果に関係なく「自分はこれでいいのだ」と受け入れる、いわば“心の土台”のようなもの。
一方、自己効力感(セルフエフィカシー)は「この仕事ならやり遂げられる」という“未来の成功を信じる力”です。



この二つは、それぞれ独立した大切な概念なのです。
職場のシーンで考えると、エフィカシーは「このプレゼン、自分なら成功させられる!」という未来に向けた自信。
自己肯定感は「たとえこのプレゼンがうまくいかなくても、自分の価値は変わらない」という、どっしりとした自己評価です。



このように、時間軸が違うと考えると分かりやすいでしょう。
管理職として部下の指導を行う際、「君は価値ある存在だ」(自己肯定感)ではなく「君ならこの課題を解決できる」(エフィカシー)という声かけを使い分けることで、より効果的な人材育成が可能になります。
苫米地英人によるエフィカシー理論の解説
認知科学者の苫米地英人氏は、「コーチングとは何か?」という問いに対して「エフィカシーを上げること」と定義し、これがコーチングの作業そのものだと位置づけています。
苫米地氏は、カーネギーメロン大学で計算言語学の博士号を取得した認知科学者として、バンデューラの理論をベースに独自のコーチング理論を発展させました。



苫米地氏の理論で特に特徴的なのは、エフィカシーを「ゴールを達成できる能力の“自己”評価」と位置づけている点です。
つまり、「他人の評価は関係ない」「過去の実績さえも関係ない」、純粋に自分が未来のゴールを達成できると信じる力こそがエフィカシーなのだと強調しています。
苫米地氏は「ゴール」「エフィカシー」「アファメーション」を組み合わせた実践法を体系化し、企業でのコーチング導入に活用されており、「過去の実績に関係なく、ゴール達成への確信を高める」アプローチは、新人や中途採用者の早期戦力化に特に有効とされています。
エフィカシーが発揮される3つの場面


エフィカシーは、特定の課題に対する自信のこと。
つまり、課題の数だけエフィカシーは存在するとも言えます。



ここでは、特にビジネスシーンで重要となる代表的な3つのエフィカシーが発揮される場面を見ていきましょう。
あなたのチームのメンバーは、どの場面での自信が強いでしょうか?
- 自己統制的自己効力感の特徴と職場での活用方法
- 社会的自己効力感がチームに与える具体的な影響
- 学業的自己効力感が継続学習や成長に果たす役割
場面1:自分を律して目標管理する力(自己統制的自己効力感)
自分を律して目標管理する力、目標達成のために「自分の行動や感情をうまくコントロールできる」と信じる力のことです。
例えば、困難なタスクを前にしても、計画を立て、誘惑に負けず、粘り強く取り組める自信を指します。
エフィカシーの根幹ともいえる重要な感覚です。
この自信が強い人は、自分の強みや弱みを客観的に把握しているため、目の前のタスクに対して「どうすれば達成できるか」という道筋を冷静に描くことができます。
職場では、新しいプロジェクトを任された際に現実的な見積もりができたり、苦手な領域では適切にサポートを求めたりする行動として現れます。



管理職として部下の自己統制的自己効力感を高めるには、定期的な1on1で部下自身に得意な業務や困っている点を言語化させ、客観的なフィードバックを提供することが効果的です。
場面2:周囲と円滑な関係を築く力(社会的自己効力感)
社会的自己効力感とは、他者とのコミュニケーションやチームワークといった社会的な場面で、「自分はうまくやっていける」と信じる力です。
多様なメンバーと協力し、良好な人間関係を築けるという自信は、現代の組織において不可欠な要素です。
現代の組織では個人の能力だけでなく、チームワークやコミュニケーション能力がますます重要視されており、この能力が高い人は困難な人間関係の問題にも積極的に取り組む傾向があります。
具体的には、意見の対立がある会議でも話し合いによる解決を信じて発言したり、新人や他部署のメンバーとも自然にコミュニケーションを取ったりする行動が見られます。
例えば、意見が対立しがちな会議でも、この自信がある人は「話し合えば、きっと良い着地点が見つかる」と信じて臆せず発言できるのです。



このような存在は、チームのコミュニケーションを活性化させ、風通しの良い職場づくりに貢献します。
場面3:新しいことを学び、成長する力(学業的自己効力感)
学業的自己効力感とは、新しい知識やスキルの習得といった「学ぶ場面」において、「自分ならきっと理解し、身につけられる」と信じる力のことです。
未知の領域へ挑戦する際の、いわば「知的な体力」とも言えるでしょう。
DXやAIの導入など、変化の激しい現代では、すべてのビジネスパーソンに継続的な学びが求められます。
この自信を持つ人は、新しいツールの導入や未知の分野への挑戦に対しても、「学べばできるようになる」と前向きに捉え、積極的にスキルアップに励むことができるのです。
職場では、新しいシステム導入時に前向きに学習に取り組んだり、資格取得や研修参加に積極的な姿勢で臨んだりする行動として現れます。
また、失敗を「学習の機会」と捉えて改善に向けて継続的に努力する特徴があります。
部下の学業的自己効力感を高めるには、学習プロセスそのものを評価し、取り組み自体を認めることで継続的な成長マインドを育てることが重要です。
エフィカシーが高い人にはどんな特徴があるか?


この章では、エフィカシーが高い人の特徴について紹介します。
エフィカシーが高い人には主に以下の4つの特徴があります。
- しなやかなポジティブさで、困難を「チャンス」と捉える
- 強い当事者意識で、決して他人事にしな
- 小さな成功体験を「自信のガソリン」にするのが上手
- 逆境でも折れない「心のしなやかさ」を持っている
特徴1:しなやかなポジティブさで、困難を「チャンス」と捉える
エフィカシーが高い人は、困難な壁にぶつかったとき、「どうせ無理だ」と諦めるのではなく、「どうすれば乗り越えられるだろう?」と自然に考えられる、しなやかなポジティブさが特徴です。
問題を避けるのではなく、むしろ「成長のチャンス」として積極的に向き合います。
彼らにとって困難な課題は「避けるべき脅威」ではなく「攻略すべきクエスト」のようなもの。
だからこそ、創造的なアプローチで解決策を探し、結果としてチーム全体の問題解決能力を引き上げる力になるのです。
職場では、新規事業の立ち上げで予算削減が必要になった際に「制約があるからこそ創意工夫のチャンス」と捉えて代替案を提案したり、システム障害が発生した際に「これを機に業務プロセスを見直そう」と建設的に対応したりする行動が見られます。



管理職としては、困難な状況を「成長の機会」として再定義する言葉がけが効果的です。
特徴2:強い当事者意識で、決して他人事にしない
エフィカシーが高い人は、「誰かがやってくれるだろう」とは考えません。自分の行動が結果を変えると信じているため、「これは自分の仕事だ」という強い当事者意識を持ち、責任感を持って業務に取り組みます。
この責任感と当事者意識は、エフィカシーの核心的要素である「自分の行動で結果を変えられる」という確信から生まれており、エフィカシーが高い社員は指示待ちをせず自律的に動く傾向が強く、チームの生産性向上に大きく貢献することが報告されています。
例えば、プロジェクトで問題が起きれば、率先して「自分が解決策を見つけよう」と動き出します。
売上目標が未達のときも、景気や他人のせいにするのではなく、「自分のやり方で、もっと改善できる点はないか?」と内省できるのです。



部下の当事者意識を育てるには、業務の意味と影響範囲を明確に伝えることが重要です。
特徴3:小さな成功体験を「自信のガソリン」にするのが上手い
エフィカシーが高い人は、過去の成功体験を「自信のガソリン」として、次の挑戦へのエネルギーに変えるのが得意です。
「あの時も乗り越えられたから、今回もきっと大丈夫」という感覚が、彼らを前進させます
心理学者のバンデューラも、エフィカシーを高めるには「実際にやり遂げた経験(達成経験)」が最も重要だと述べています。
エフィカシーが高い人は、どんなに小さな成功でも「できた!」という手応えをしっかりと記憶し、それを自信の源泉にできるのです。
成功体験の蓄積が豊富な社員は新規業務への適応速度が早く、イノベーション創出にも積極的であることが確認されています。
職場では、新しいプレゼンテーションの機会で「前回の顧客提案が成功したから、今回も工夫すれば大丈夫」と自信を持って準備したり、チームリーダーを初めて任された際に「過去のプロジェクト管理経験を活かせば成功できる」と前向きに取り組んだりする行動が見られます。
特徴4:逆境でも折れない「心のしなやかさ」を持っている
エフィカシーが高い人は、プレッシャーや逆境に強く、冷静さを失いません。
「自分なら何とかなる」という根っこの自信が、精神的な安定につながり、目先のトラブルに一喜一憂せず、長期的な視点で物事を捉えることを可能にします。
彼らは「自分なら何とかできる」という確信があるため、ストレスフルな状況でも過度に不安にならず、解決策の検討に集中できることが特徴です。
また、困難を「成長の機会」として捉える思考パターンにより、ストレス要因そのものを前向きに解釈する能力があり、エフィカシーが高い社員は燃え尽き症候群のリスクが低く、長期間にわたって高いパフォーマンスを維持する傾向があると言われています。
例えば、締切間近の重要プロジェクトでも、「焦っても仕方ない。計画通りに進めれば大丈夫」と冷静に対処できます。
また、顧客からの厳しい意見も、「ありがたい改善のヒントだ」と前向きに受け止め、次へと活かすことができるのです。
エフィカシーをどうやって測定・評価するのか?


この章では、エフィカシーの測定・評価方法について紹介します。
エフィカシーの測定・評価には主に以下の3つの方法があります。
- 一般性自己効力感尺度を活用した科学的な評価手法
- 日常業務での部下のエフィカシーを見極める観察チェック法
- チーム・組織全体の集団効力感を測定する指標と活用方法
方法1:アンケートで客観的に測定する(GSESの活用)
エフィカシーは、「一般性自己効力感尺度(GSES:General Self-Efficacy Scale)」といった心理尺度を用いて、ある程度客観的に測定することができます。
これは、バンデューラの理論を基に日本の研究者によって開発された信頼性の高いアンケート形式のツールで、人材育成の効果測定などで活用されています。
16項目の質問に「はい」「いいえ」で回答するシンプルな構成でありながら、エフィカシーの「大きさ」「一般性」「強さ」の3つの要素を総合的に測定できる優れた尺度です。
管理職として部下のエフィカシー測定にGSESを活用する際は、評価のためではなく成長支援のツールとして位置づけ、測定結果をもとに1on1で対話することが重要です。
方法2:日々の言動から「見立てる」(行動観察
専門的なツールを使わなくても、日々の業務における部下の言動を観察することで、エフィカシーの高低をある程度「見立てる」ことは可能です。
特に、「困難への向き合い方」「仕事への当事者意識」「新しいことへの学習意欲」「プレッシャー下での反応」という4つの観点に注目してみましょう。
エフィカシーは内面的な確信であるため直接的な測定は困難ですが、行動や言動として必ず外部に現れる特性があります。
エフィカシーは内面的な自信のため、行動観察だけで100%正確に測ることはできません。しかし、その人の行動や言葉には、自信の度合いが滲み出るものです。
例えば、新しい仕事を依頼した時の第一声や、トラブル発生時の動き方などに注目してみましょう。
具体的には、新しい業務を依頼した際の反応や、トラブル発生時の解決策提案の積極性、失敗した際の学習姿勢などを観察ポイントとして活用します。



効果的な観察のために、エフィカシーチェックシートを作成し、月1回程度の頻度で各部下の行動を記録することをおすすめします。
方法3:チーム全体の「やれる感」を測る(集団的エフィカシー)
個人だけでなく、「私たちチームなら、この困難な目標も達成できるはずだ!」というチーム全体の自信=「集団的エフィカシー」も重要です。
これは、生産性や離職率といった業績データに加え、「チームで困難な課題も解決できると思うか?」といった簡単な組織アンケートを組み合わせることで、その度合いを測ることができます。
個々のメンバーのエフィカシーが高くても、チームとしての自信が低ければ、組織力は最大化されません。
1+1が2以上になるような相乗効果を生むためにも、チーム単位での「やれる感」を可視化することが大切なのです。
測定指標として、定量面では月次売上目標達成率やプロジェクト完了率、定性面では「チームで困難な課題も解決できると思う」といった質問を含む組織アンケートを四半期ごとに実施し、測定結果をダッシュボード化して全社で共有することが効果的です。
エフィカシーが組織にもたらすメリット


この章では、エフィカシーが組織にもたらすメリットについて紹介します。
エフィカシーが組織にもたらすメリットには主に以下の内容があります。
- 業績向上と生産性アップによる組織力強化
- 従業員のモチベーション向上と自律的な行動促進
- 社内コミュニケーションの活性化と信頼関係構築
- チャレンジ精神の醸成による組織のイノベーション創出
メリット(1)業績向上と生産性アップ
エフィカシーが高い組織では、従業員が「自分たちなら必ず目標を達成できる」という確信を持って業務に取り組むため、業績向上と生産性の大幅なアップが実現されます。
エフィカシーが高い従業員は、成長意欲をもった目標を掲げ、最後までやり切る姿勢を体現するのが特徴です。
その結果、仕事で高い業績をあげることができます。。
困難な課題に直面しても「何とかなる」という前向きな思考で取り組むため、組織全体の実行スピードが向上し、結果として業績に直結する成果を創出します。



管理職としては、チーム全体のエフィカシーを段階的に高め、小さな成功体験を積み重ねることで集団効力感を育てることが重要です。
メリット(2)従業員のモチベーション向上
エフィカシーが高まることで、従業員は自分の能力と成果への確信を持つようになり、内発的なモチベーションが大幅に向上し、自律的に行動する組織文化が形成されます。
エフィカシーは「自分なら達成できる」という確信であるため、外的な報酬や評価に依存しない持続的なモチベーションを生み出すのです。
エフィカシーが高い社員は指示待ちをせず自律的に動く傾向が強く、チームの生産性向上に大きく貢献すると言われています。
また、エフィカシーが高い人は前向きで意欲的に動けるため、周囲にも良い影響を与え、組織全体のモチベーション向上につながる相乗効果があります。
従業員のモチベーション向上には、個人の強みを活かせる業務配分と、小さな成功体験を積み重ねられる環境づくりが重要です。
メリット(3)社内コミュニケーションの活性化
エフィカシーが高い従業員は積極的なコミュニケーションを取る傾向があり、組織全体の情報共有が促進され、信頼関係に基づいた円滑なチームワークが実現されます。
社会的自己効力感が高い人は、他者とのコミュニケーションや人間関係の構築において「自分は適切に行動し、良好な関係を築ける」という確信を持っています。
社会的自己効力感の高い従業員がいるチームは、コミュニケーションが活性化し、社内の雰囲気が良好になる傾向があると言われているのです。
また、エフィカシーが高い人は困難な人間関係の問題にも積極的に取り組み、建設的な解決策を見出そうとするため、組織内の対立や課題の早期解決にも貢献します。
社内コミュニケーション活性化のために、成功したコミュニケーション事例を積極的に評価し、社会的な能力を具体的に認めることが重要です。
メリット(4)チャレンジ精神の醸成
エフィカシーが組織に浸透することで、従業員は新しい取り組みや困難な課題に対して「挑戦してみよう」という前向きな姿勢を示すようになり、組織全体のイノベーション創出能力が大幅に向上します。
エフィカシーが高い人は、困難な課題を「避けるべき脅威」ではなく「習得すべき挑戦」として受け止める特徴があります。
成功体験の蓄積が豊富な社員は新規業務への適応速度が早く、イノベーション創出にも積極的であると言われているのです。
また、学業的自己効力感が高い人は、困難な課題や新しい分野にも「学習すれば克服できる」と考えるため、継続的なスキルアップと組織の競争力向上に貢献します。
組織のチャレンジ精神を醸成するには、失敗を恐れない文化づくりと、挑戦への適切な評価システムが重要です。
エフィカシーが高すぎることによるデメリット


この章では、エフィカシーが高すぎることによるデメリットについて紹介します。
エフィカシーが高すぎることによるデメリットには主に以下の内容があります。
- 周囲との温度差が生じるリスクとチームバランスへの影響
- 能力への過信による判断ミスと現実乖離の問題
デメリット(1)周囲との温度差が生じるリスク
エフィカシーが極端に高い人材は、同僚やチームメンバーとの間に温度差を生じさせ、組織内での孤立や摩擦を引き起こすリスクがあり、結果的にチーム全体のパフォーマンス低下を招く可能性があります。
エフィカシーが高い人は「自分なら必ずできる」という強い確信を持つため、同じレベルの意欲や自信を持たない同僚に対して無意識のうちに高い期待を抱いたり、理解を示せなくなったりする傾向があるのです。
極端にエフィカシーが高い個人がチーム内にいる場合、他メンバーが劣等感を感じたり、プレッシャーを受けたりして、かえってチーム全体のエフィカシーが低下するケースが報告されています。
周囲との温度差を防ぐためには、エフィカシーが高い人材に対して多様な視点の価値を理解させる教育が重要です。
デメリット(2)能力への過信による判断ミス
エフィカシーが過度に高くなると、自分の能力を客観視できなくなり、現実的なリスク評価を怠ったり、無謀な挑戦をしたりして、組織に重大な損失をもたらす判断ミスを犯すリスクが高まります。
エフィカシーの本質は「自分なら達成できる」という確信ですが、これが度を越すと現実の制約や困難を軽視する傾向が生まれてしまうのです。
また、過信により他者からの助言や警告を聞き入れなくなり、チェック機能が働かなくなることで、組織全体がリスクにさらされる危険性もあります。
能力への過信を防ぐためには、重要な判断を行う前には必ず第三者による客観的なレビューを実施し、リスク分析を義務化することが効果的です。
エフィカシーを高めるためにできること


この章では、エフィカシーを高めるためにできることについて紹介します。
エフィカシーを高めるためにできることには主に以下の内容があります。
- コーチングによる意識変革と自己効力感の向上手法
- アファメーション活用による確信の強化と実践方法
- コンフォートゾーンの適切な設定によるチャレンジ環境の構築
- 小さな成功体験の積み重ねによる段階的なエフィカシー向上
- 知識とスキルの継続的なインプットによる能力基盤の強化
コーチングで意識を変える
コーチングは、エフィカシー向上において最も効果的な手法の一つであり、部下の内面にある「自分なら達成できる」という確信を引き出し、行動変容を促す強力なツールです。
認知科学者の苫米地英人氏が「コーチングとは何か?」という問いに対して「エフィカシーを上げること」と定義しているように、コーチングの本質はエフィカシーの向上にあります。
効果的なコーチング質問
「この課題をクリアするために、あなたの強みをどう活かせるか?」
「過去に似たような困難を乗り越えた経験はある?」
といった自己効力感を引き出す質問を活用し、週1回30分程度の1on1を定期化することで部下のエフィカシーを段階的に高められます。
アファメーションを効果的に活用する
アファメーションは、肯定的な言葉を繰り返し唱えることで潜在意識にエフィカシーを刷り込む手法であり、適切に実践することで「自分なら必ず達成できる」という確信を強化できます。
苫米地理論では「ゴール」「エフィカシー」「アファメーション」が三位一体となってコーチング効果を発揮するとされ、アファメーションはエフィカシーを定着させる重要な要素です。
効果的なアファメーション
営業職なら「私は顧客のニーズを的確に把握し、最適な提案で必ず成約を取る」
管理職なら「私はチームメンバーの能力を最大限に引き出し、困難なプロジェクトも必ず成功に導く」
といった現在形で断定的な表現を使い、個人の目標や強みに基づいたオリジナル文を作成することが重要です。
コンフォートゾーンを適切に設定する
コンフォートゾーンを適切に設定し、部下が「少し背伸びすれば達成できる」レベルの挑戦機会を提供することで、エフィカシーを段階的かつ着実に向上させることができます。
コンフォートゾーンとは、個人が安心して行動できる範囲のことで、エフィカシー向上には現在のコンフォートゾーンを少しずつ拡張することが重要です。
具体的には、新人営業には月5件の商談から始めて段階的に10件、15件と増やしたり、プレゼンが苦手な社員には社内の小さな会議から始めて徐々に規模を拡大したりするアプローチが効果的。
新しい挑戦を提案する際は、「君の○○のスキルがあれば、この課題もクリアできるはず」と根拠を示し、必要なサポート体制も整えることで安心感を提供することが大切です。
小さな成功体験を積み重ねる
小さな成功体験の積み重ねは、エフィカシー向上において最も確実で効果的な方法であり、バンデューラの自己効力感理論でも「達成経験」として最重要要因に位置づけられています。
バンデューラの理論によると、直接的達成経験はエフィカシーを高める最も重要な要因とされており、どんなに小さな成功でも「自分にはできる」という確信の積み重ねになります。
具体的には、大きなプロジェクトを週単位のマイルストーンに分割して達成感を味わわせたり、日報や週報で小さな改善や工夫を積極的に評価したりする取り組みが効果的です。



成功体験を単なる偶然ではなく、本人の能力や努力の結果として認識させることで、継続的なチャレンジ意欲を維持できますよ。
知識とスキルの継続的なインプット
継続的な知識とスキルのインプットは、エフィカシーの基盤となる実際の能力を向上させ、「学習すれば必ず習得できる」という学業的自己効力感を高める重要な要素です。
エフィカシーは根拠のない自信ではなく、実際の能力に裏打ちされた確信であるため、継続的な学習による能力向上が不可欠です。
DX化やAI技術の進歩により、現代のビジネスパーソンには継続的な学習と成長が求められており、学習習慣自体がエフィカシー向上につながります。
業務に直結する専門書籍の読書会開催や、オンライン研修への参加支援、社内勉強会での知識共有など、多様な学習機会を提供し、学習成果を実際の業務で活用する機会も併せて提供することが重要です。
エフィカシーを下げてしまうNG行動とは?


この章では、エフィカシーを下げてしまうNG行動について紹介します。
エフィカシーを下げてしまうNG行動には主に以下の内容があります。
- ネガティブフィードバックの受け止め方と適切な指導法への転換
- 現実離れした目標設定がもたらすリスクと段階的アプローチ
- 失敗ばかりに意識が向く思考習慣の改善と成長マインドの醸成
ネガティブフィードバックの受け止め方
批判的で否定的なフィードバックや、能力そのものを否定するような指導方法は、部下のエフィカシーを大幅に低下させ、長期的な成長阻害要因となる危険な管理手法です。
「君には営業の才能がない」「いつも同じミスを繰り返すね」といった能力否定や人格攻撃、「他の人はできているのに」といった比較による評価は、部下の「自分なら達成できる」という確信を根底から崩してしまいます。
エフィカシーを保護するためには、行動に焦点を当てた建設的な指摘を行い、「3つの良い点と1つの改善点」の比率でフィードバックすると効果的だと言われているため、参考にしてくださいね。
現実離れした目標設定のリスク
部下の現在の能力レベルを大幅に超える現実離れした目標設定は、継続的な失敗体験を生み出し、エフィカシーの深刻な低下と学習性無力感を引き起こすリスクの高い行為です。
適切なエフィカシー向上には、現在の能力より若干高いレベルの課題設定が最も効果的とされているため、過度に高い目標は逆効果となります。
新人営業に初月から月50件の商談目標を課したり、プレゼン未経験者にいきなり大規模な顧客向け発表を任せたりするような無謀な目標設定は、部下に「自分には無理」という確信を植え付け、長期的な成長意欲を削いでしまいます。
失敗ばかりに意識が向く思考習慣
失敗や問題点ばかりに焦点を当て、成功体験や成長を見過ごす思考習慣は、部下のエフィカシーを継続的に低下させ、組織全体の学習・成長文化を阻害する深刻な要因です。
人間の脳は本来ネガティブな情報に注意を向けやすい「ネガティビティバイアス」を持っているため、意識的に成功体験や改善点を認識する習慣を作らなければ、自然とエフィカシーは低下していきます。
会議で問題点ばかりを議論したり、「なぜできなかったか」という質問ばかりを繰り返したりする思考習慣を改善し、成功体験の振り返りを習慣化することで、ポジティブな学習文化を醸成することが重要です。
まとめ


本記事では、未来の目標達成への自信を意味する「エフィカシー」について、その意味や自己肯定感との違い、組織にもたらす多大なメリットを解説しました。
最も重要なのは、エフィカシーが感覚的な精神論ではなく、具体的なマネジメント手法によって高められるという事実です。
意図的な「小さな成功体験」の創出や、コーチング、アファメーションといった関わり方は、指示待ちだった部下を自律的な人材へと変える力を持っています。
これによりチームの生産性が向上し、メンバー一人ひとりが当事者意識を持って働く組織づくりが可能となります。
エフィカシーを高めることは、単に業績向上を狙うだけでなく、個々のメンバーが自らの役割に責任と主体性を持ち、真の「生産者」として組織に貢献する土壌を育てることにつながりますよ。



まずは一つでも、明日からの1on1やフィードバックで実践し、チーム変革の第一歩を踏み出しましょう。
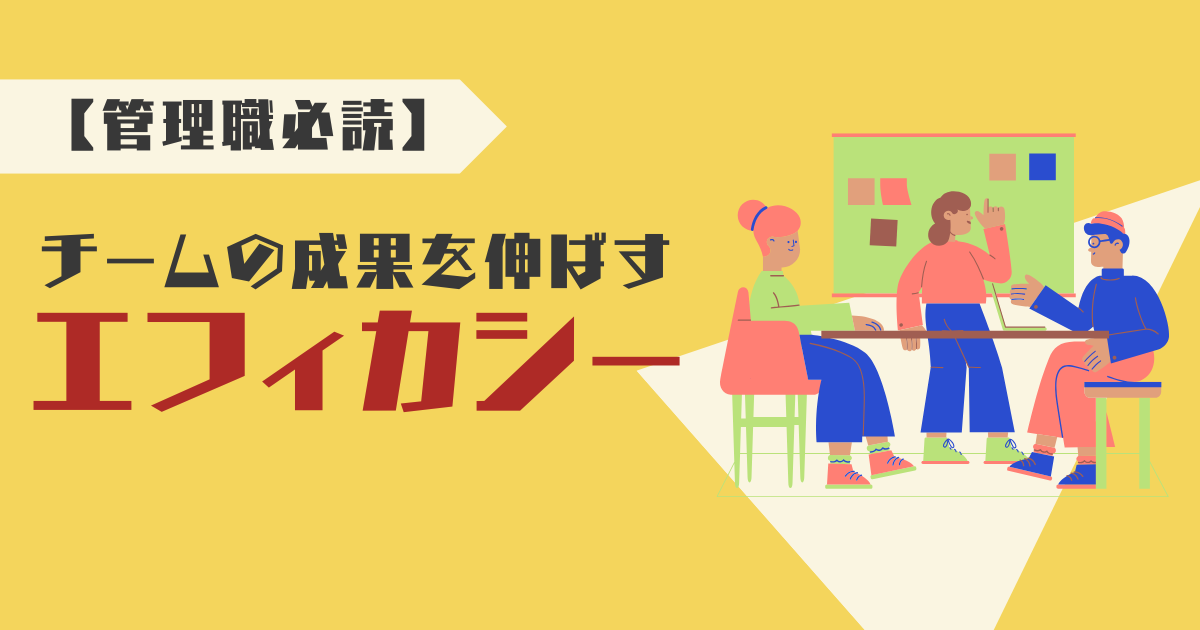


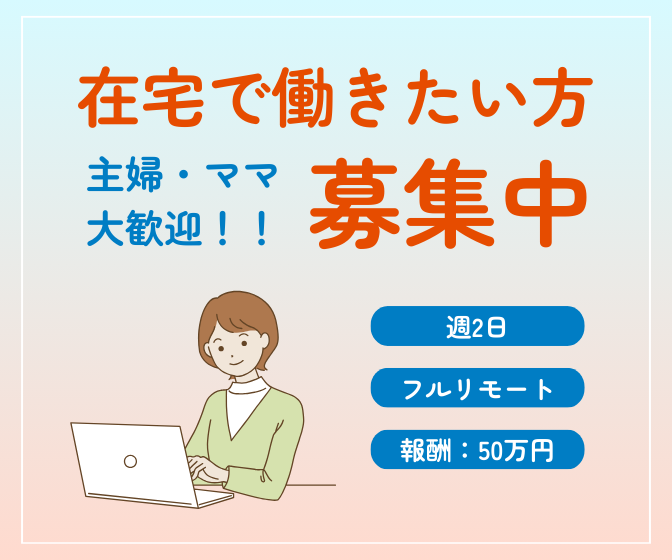

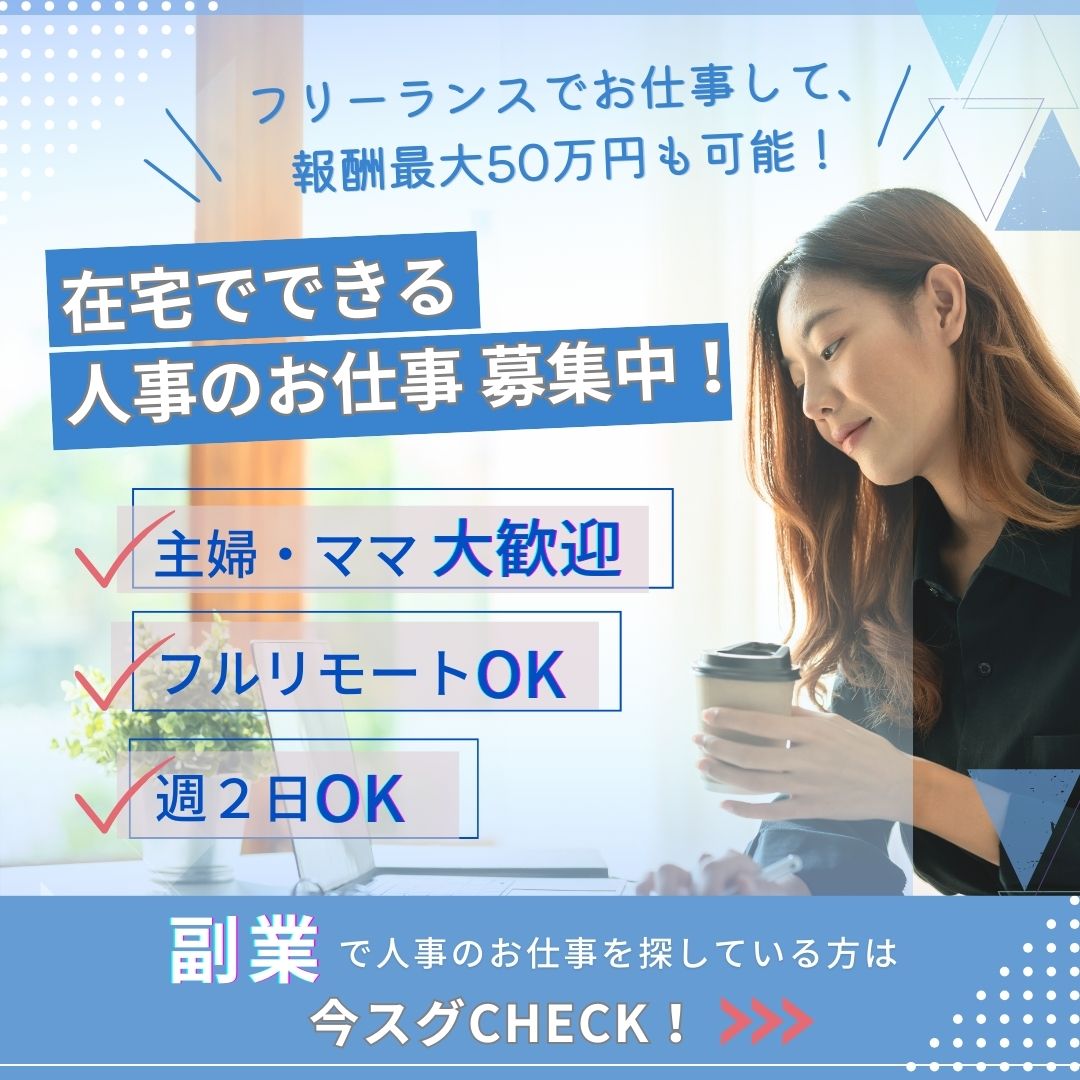

コメント