- マタハラとは、「職場において、妊娠・出産・育児休業等の利用を理由に行われる不利益な取扱いや嫌がらせ」のことです。
- 就業規則にマタハラとは何かの定義、禁止行為の具体例、違反時の処分内容、相談窓口の設置を明記する必要があります。
- 主張を「事実」として裏付ける客観的な証拠を、日頃から記録しておくことが、自分を守る最大の武器になります。
「もしかして、これってマタハラ?」と不安に思う方、または企業の対策担当者として「マタハラとは何か」を正確に知りたい方は多いのではないでしょうか?。
この記事を読めば、ご自身の状況や次に何をすべきかが明確になります。
本記事では、「マタハラとは」その意味を厚生労働省の指針に基づき簡単に解説し、男性の育休に関する例や「また腹とは」といった誤解も解消します。

妊娠をして周囲に理解してもらえなくても、一人で抱え込まないでください。
働く女性が安心してキャリアを継続できる環境づくりのための、最初の一歩を踏み出しましょう。
マタハラとは?意味や種類を簡単に解説


「上司に妊娠を報告したら、急に態度が冷たくなった…」「これってマタハラ?」そんな不安を感じたときに、まず知っておくべき基本的な知識を、厚生労働省の定義に基づいてわかりやすく解説します。
ご自身の状況がマタハラに当たるか判断できるよう、マタハラの2つのタイプや、男性の育休に関する「パタハラ」との違いも整理していきましょう。
- 厚生労働省による正式な定義と法的根拠
- 制度利用への嫌がらせ型と状態への嫌がらせ型の2つの類型
- 男性の育休に関わるパタハラとの違いと関係性
定義(1)厚生労働省によるマタハラの定義
マタハラ(マタニティハラスメント)とは、厚生労働省によると「職場において、妊娠・出産・育児休業等の利用を理由に行われる不利益な取扱いや嫌がらせ」のことです。
具体的には、妊娠したり、母親になったりした女性従業員が職場で受ける、精神的・肉体的な苦痛を伴う行為全般を指します。
こうした行為は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法といった法律で固く禁じられており、企業にはハラスメントを未然に防ぐための措置を講じる義務が課せられているのです。
具体的な違反例としては、妊娠報告後の降格や減給、育休申請の拒否、つわりを理由とした退職強要などが該当します。
労働契約法第5条の安全配慮義務の観点からも、企業は妊娠中の従業員に対して適切な配慮を行う必要があります。
もし、妊娠を報告したことで上司や同僚から心ない言動を受け不安に感じたら、こうした法律が「働く女性の権利」を守るための強い盾となることを、ぜひ覚えておいてください。
定義(2)制度利用への嫌がらせ型と状態への嫌がらせ型
マタハラは、その嫌がらせの内容によって、大きく2つのタイプに分けられます。
1つは育休などの「制度の利用」を邪魔するタイプ、もう1つは妊娠したこと「そのもの(状態)」を非難するタイプです。
制度利用への嫌がらせ型とは、育児休業や時短勤務などの法的に認められた制度の利用を妨害したり、制度利用を理由として不利益な取り扱いを行う行為です。
具体例として「育休を取るなら昇進は諦めろ」という発言や、産前休暇取得による賞与減額などがあります。
一方、状態への嫌がらせ型は、妊娠や出産という生理的な状態そのものに対する嫌がらせで、つわりで体調不良の際に「妊婦は使えない」と発言されたり、妊娠を理由に重要な業務から外されるケースが該当します。
どちらの型も法律で禁止されており、人事・総務担当者は、これら両方のハラスメントに対応できるよう、具体的な防止策を就業規則などに明記し、管理職向け研修でケーススタディを取り入れるなどの対策が不可欠です。
定義(3)男性の育休に関わるパタハラとの違い
パタハラとは、パタニティハラスメントの略で、男性の育児参画や育児休業取得を阻害する嫌がらせ行為を指します。
マタハラと同様に育児・介護休業法を法的根拠とし、企業には防止義務がありますが、社会的背景や当事者への影響に違いがあります。
パタハラの具体例には「男が育休なんて取るな」という上司の発言や、育休申請した男性社員の昇進見送りなどがあり、性別役割分業意識という社会的偏見が根底にあります。
2022年の育児・介護休業法改正により男性の育休取得促進が義務化されたことで、パタハラ防止も企業の重要課題となっています。
マタハラとパタハラは、同じ法律が根拠となり、企業に防止義務がある点は共通です。
しかし、パタハラの背景には「男のくせに育休なんて」といった特有の偏見や、男性自身の心理的なためらいが存在します。
企業としては、これらを個別の問題とせず、誰もが働きやすい職場を作るという大きな視点から一体的に対策し、多様な働き方への理解を深める風土づくりに取り組むことが、本質的な解決につながります。
これってマタハラ?言動の具体例チェック


ここでは、職場で実際に言われがちな「マタハラ発言」を4つのパターンに分けてご紹介します。
もし、あなたが言われた言葉がこれらに当てはまるか、チェックしてみてください。
会社側の方は、自社でこうした言動がないかを確認するきっかけとしてください。
マタハラの具体例には主に以下の内容が挙げられます。
- 「迷惑だ」など妊娠を否定する発言パターン
- 「休むなら辞めろ」など解雇を示唆する言動パターン
- 「評価を下げる」など不利益な処遇を示唆するパターン
- つわり等への無理解な発言や態度のパターン
具体例(1)「迷惑だ」など妊娠を否定する発言
「迷惑だ」「困る」「なぜこの時期に」など、妊娠そのものを否定的に捉える発言は典型的なマタハラであり、男女雇用機会均等法違反に該当します。
このような言動は妊娠を理由とした就業環境の悪化を招く「状態への嫌がらせ型」のマタハラとして厚生労働省の指針でも明確に禁止されているのです。
上司からの「なんで今妊娠したの?」「プロジェクトの途中で困る」「チームに迷惑をかけることを考えなかったの?」といった発言や、同僚からの「私たちにしわ寄せが来る」「独身者ばかり損をする」「計画性がない」といった言動が該当します。
もしこうした発言を受けてしまったら、まずは冷静に「いつ、どこで、誰に、何を言われたか」をメモに残しましょう。



それが、後で人事部や外部機関に相談する際の重要な証拠となります。
企業側としては、「妊娠はおめでたいことであり、会社全体でサポートする」というポジティブな方針を明確に打ち出し、特に管理職には、妊娠報告を受けた際の「最初の対応」がいかに重要かを研修で徹底することが求められます。
具体例(2)「休むなら辞めろ」など解雇を示唆する言動
産休や育休の取得を理由とした退職の示唆や解雇予告は、育児・介護休業法第10条に明確に違反する重大なマタハラです。
直接的な退職強要として「産休を取るなら辞めてもらう」「育休明けに席はない」「出産したら契約更新はしない」といった発言や、間接的な退職示唆である「このままだと査定に響く」「復帰しても仕事はない」「転職を考えた方がいいのでは」といった言動が該当します。
過去の裁判では、妊娠を理由とした降格は原則として違法であるとの判断が最高裁で示されています。
ケースによっては企業に数百万円単位の損害賠償が命じられることもあり、企業にとって極めて大きなリスクです。
もし、こうした退職を迫るようなことを言われたら、その場で安易に同意してはいけません。
会話を録音したり、メールを保存したりして客観的な証拠を確保し、速やかに労働局や弁護士といった社外の専門機関に相談してください。
企業は就業規則に明確な禁止条項を設け、違反者への処分規定も整備することが求められます。
具体例(3)「評価を下げる」など不利益な処遇を示唆
妊娠・出産・育休取得を理由とした降格、減給、賞与減額などの不利益処遇の示唆は、男女雇用機会均等法第9条違反の典型例です。
昇進・昇格の阻害として「妊娠中は責任ある仕事は任せられない」「管理職は無理」「評価は期待できない」といった発言や、給与・賞与への影響を示唆する「時短勤務なら給与カット」「産休中は賞与なし」「査定では不利になる」といった言動が該当します。
また、配置転換の強要として「軽い部署に移ってもらう」「重要なプロジェクトから外す」「顧客対応はできない」といった一方的な決定も問題となります。
近年の裁判例では、妊娠を理由とした一方的な配置転換や降格について、企業側が敗訴するケースが目立っています。
処遇の変更には、本人の明確な同意と、業務上の客観的かつ合理的な必要性の両方が求められることを、企業は肝に銘じるべきです。
当事者は処遇変更の理由を文書で確認し、不当な場合は社内外の相談窓口を活用することが大切です。
具体例(4)つわり等への無理解な発言や態度
つわりや妊娠に伴う体調変化への無理解な発言や配慮不足は、労働契約法第5条の安全配慮義務違反にあたるマタハラです。
体調不良への無理解として「つわりは病気じゃない」「気持ちの問題」「甘えている」「他の人はできていた」といった発言や、配慮の拒否である「休憩は認められない」「軽易業務への転換は無理」「通院時間は有給を使え」といった対応が該当します。
さらに、業務強要として「つわりでも残業は必要」「出張は行ってもらう」「重いものも運んで」といった指示も問題となります。
妊娠中の女性には時間外労働の制限や危険業務の就業制限など、労働基準法による保護規定があり、企業には母性健康管理指導事項連絡カードに基づく措置を講じる義務があります。
企業としては、産業医と連携して相談しやすい体制を整えたり、妊娠中の社員への具体的な配慮事項をまとめたハンドブックを作成したりするなど、現場の管理職が迷わず対応できる仕組みづくりが不可欠です。
マタハラが法律違反となる3つの根拠


マタハラは、単なる「職場の雰囲気」の問題ではなく、明確に法律で禁止されている行為です。
ここでは、あなたを守る「盾」となる3つの主要な法律を根拠に、なぜマタハラが許されないのかを解説します。
この知識は、いざという時に会社と話し合うための「武器」にもなります。
マタハラの法的根拠には主に以下の内容があります。
- 男女雇用機会均等法が禁じる不利益な取扱いの詳細
- 育児・介護休業法に基づく権利の侵害パターン
- 労働基準法が定める産前産後休業の権利と保護規定
根拠(1)男女雇用機会均等法が禁じる不利益な取扱い
男女雇用機会均等法第9条は、妊娠・出産・産前産後休業等を理由とする解雇や不利益取扱いを明確に禁止しており、マタハラとは何かを法的に定義する最も重要な根拠となっています。
この法律では、妊娠報告後の降格、減給、賞与不支給、配置転換、業務内容の変更などが具体的に禁止されており、企業には就業規則等での方針明確化・周知、相談窓口設置、適切な事後対応と再発防止措置を講じる義務があるのです。
違反した場合は厚生労働大臣による勧告・公表、20万円以下の過料が科せられる可能性があります。
2017年の最高裁判決では妊娠による降格が原則違法と判断され、企業の損害賠償責任が確立されました。
もし妊娠を理由に不利益な扱いを受けたと感じたら、この「均等法第9条違反」を根拠に、労働局や弁護士へ相談することをためらわないでください。
また、2020年6月1日に改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行され、2022年4月1日からは中小企業にも義務化されました。
これは、マタハラ防止にも関連する重要な法改正です。
企業側は就業規則にマタハラ禁止条項を明記し、管理職への教育を徹底する必要があります。
根拠(2)育児・介護休業法に基づく権利の侵害
育児・介護休業法第10条は、育児休業の申出・取得を理由とする不利益取扱いを禁止し、企業にハラスメント防止措置を義務付けています。
この法律は制度利用への嫌がらせ型マタハラの防止に重要な役割を果たしており、育休申請の拒否、育休取得者の昇進阻害、復職時の不当な配置転換、退職強要などの行為を明確に禁止しているのです。
企業には相談体制整備、職場環境改善、被害者への適切な配慮、再発防止措置を講じる義務があります。
2022年の法改正では男性の育休取得促進、ハラスメント防止措置の強化、中小企業への適用拡大が図られました。
従来の育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる柔軟な休業制度であり、男性の育休取得をさらに促進するものです。
違反時には勧告・公表、雇用環境均等室による指導、場合によっては過料が科せられます。
育休の取得を妨害されるなどのハラスメントを受けた場合は、「育児・介護休業法違反の疑いがある」として、各都道府県の労働局にある「雇用環境・均等室」に相談するのが有効な一手です。
法改正は頻繁に行われるため、人事担当者は常にアンテナを高く張り、社内制度や研修内容を最新の状態にアップデートし続けることが責務となります。
根拠(3)労働基準法が定める産前産後休業の権利
労働基準法第65条等は産前産後休業や妊娠中の軽易業務転換請求権を保障しており、これらの権利行使を妨害する行為は同法違反です。
この法律では産前6週間・産後8週間の休業、軽易業務転換請求、時間外・休日・深夜業の制限、妊婦健康診査等の時間確保が具体的に保障されています。
つわりや体調不良など妊娠に伴う身体的変化への配慮不足は、労働基準法の母性保護規定違反となる可能性があるのです。
企業には母性健康管理指導事項連絡カードに基づく措置、産業医との連携、職場環境の整備が義務付けられています。
産前産後休業の拒否、軽易業務転換の拒否、妊婦健診時間の確保拒否、危険有害業務への従事強要などの行為は禁止されており、これらの母性保護規定に違反した場合、企業には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という、ハラスメント関連法規の中でも特に重い刑事罰が科される可能性があります。
妊娠中の権利が侵害された場合は、労働基準法違反として労働基準監督署への申告を検討することが重要です。
企業は産業医や人事部門との連携体制を整備し、妊娠中の社員への配慮を制度化する必要があります。
妊娠・出産に関わる各種手当や給付金の種類と申請方法


妊娠・出産から育児休業にかけては、一時的に収入が減ることへの不安がつきものです。
しかし、その間の生活を支えるための心強い公的な給付制度が複数あります。
ここでは、安心して休むために絶対に知っておきたい、3つの主要な経済的支援について、その仕組みと申請方法を解説します。
- 産休中の収入を補う出産手当金の詳細と申請手順
- 出産費用を補助する出産育児一時金の仕組み
- 育休中の生活を支える育児休業給付金の計算方法
給付金(1)産休中の収入を補う出産手当金
出産手当金は健康保険から支給される制度で、産前産後休業中の収入減少を補う重要な給付金です。
標準報酬日額の3分の2相当額を最大98日間受給でき、妊娠中の女性が安心して産休を取得できるよう経済面でサポートします。
支給要件は健康保険加入者で産前産後休業を取得することで、支給期間は出産日以前42日間と出産日後56日間です。



多胎妊娠の場合は、産前期間が98日間に延長されます。
支給額の計算例として、標準報酬月額30万円の場合は日額約6,667円、月額換算で約20万円の支給となります。
出産手当金は健康保険の標準報酬月額を基に計算されるため、出産手当金の上限額は、健康保険の標準報酬月額の上限である139万円です。
申請手続きは「健康保険出産手当金支給申請書」を勤務先経由で健康保険組合に提出し、申請から約1~2か月後に指定口座に振り込まれます。
こうした経済的なセーフティーネットの存在は、万が一のマタハラに直面した際に「辞めても生活できない」という不安を和らげ、不当な要求に屈せず自分の権利を主張するための、大切なお守りになりますよ。
給付金(2)出産費用を補助する出産育児一時金
出産育児一時金は健康保険から一児につき50万円が支給される制度で、出産費用の経済的負担を大幅に軽減してくれます。
2023年4月より従来の42万円から50万円に増額され、平均的な出産費用をほぼカバーできる水準です。
支給要件は健康保険加入者または被扶養者が妊娠4か月以上で出産することで、正常分娩だけでなく帝王切開や早産、流産の場合も対象です。
利用方法として直接支払制度があり、医療機関が健康保険組合に直接請求することで、窓口での支払いは差額のみとなります。
小規模医療機関では受取代理制度も利用可能で、より簡便な手続きで給付を受けられます。
申請は「健康保険出産育児一時金支給申請書」と医師の証明書を提出することで行います。
人事担当者としては、従業員から妊娠報告を受けた際、会社の祝福の気持ちと共にこれらの制度を丁寧に案内し、申請をしっかりサポートする姿勢を見せることが、従業員のエンゲージメントを高め、マタハラが起きにくい信頼関係の構築に繋がるでしょう。
給付金(3)育休中の生活を支える育児休業給付金
育児休業給付金は雇用保険から支給される制度で、育休中の収入を休業前賃金の最大67%まで補償し、最長2年間受給可能です。
支給要件は雇用保険加入者で育児休業を取得し、休業前2年間に被保険者期間が12か月以上あることです。
支給率は育休開始から180日間は休業前賃金の67%、181日目以降は50%となっており、休業前賃金30万円の場合、最初の6か月間は月額約20万円が支給されます。
2025年4月1日から育児休業給付の制度が改正され、両親が共に14日以上の育休を取得するなどの要件を満たす場合、育休開始から28日間の給付率が休業前賃金の80%相当に引き上げられました。
支給期間は原則として子が1歳になるまでですが、保育所に入れない場合は最大2歳まで延長可能です。
申請手続きは勤務先がハローワークに「育児休業給付金支給申請書」を2か月ごとに提出することで行われます。
この給付金制度があるおかげで、収入減を理由に育休取得をためらう必要は大きく減ります。
また、これはマタハラで不当な退職を迫られた際に、「すぐに辞めなくても生活は守られる」という、交渉を有利に進めるための強力なカードにもなるでしょう。
企業は育休取得者への制度説明と申請手続きの代行を適切に行い、従業員が安心して育児と仕事の両立を図れる環境整備が求められています。
企業に求められるマタハラ防止の義務


マタハラを「個人の問題」で終わらせず、会社として組織的に防止することは、法律で定められた企業の義務です。
ここでは、人事・総務担当者が中心となって進めるべき、具体的な4つの防止策について解説します。これらは、従業員を守り、企業のブランド価値を守るための重要な投資です。
- 防止方針の明確化と社内への周知啓発の実施方法
- 相談窓口の設置とプライバシーの保護体制
- ハラスメント発生後の迅速で適切な対応フロー
- 業務分担の見直しなど職場環境の改善措置
対策(1)防止方針の明確化と社内への周知啓発
企業は男女雇用機会均等法第11条の3に基づき、マタハラ防止方針を明確化し、就業規則への明記と全従業員への周知を義務付けられています。
具体的には、就業規則にマタハラとは何かの定義、禁止行為の具体例、違反時の処分内容、相談窓口の設置を明記する必要があります。
周知方法として新入社員研修、管理職研修、社内イントラネット掲載、ポスター掲示、定期的なメール配信などが効果的です。
厚生労働省指針では、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止とハラスメント防止の表明が必須項目とされています。
違反した場合は労働局による指導・勧告、企業名の公表、20万円以下の過料が科せられる可能性があります。
経営トップからのメッセージとして方針を発信し、管理職への定期研修を実施することで、職場全体の意識改革を図ることが重要です。
従業員アンケートで認知度を測定し、周知の効果を継続的に検証する取り組みも求められています。
対策(2)相談窓口の設置とプライバシーの保護
企業は育児・介護休業法第25条に基づき、マタハラに関する相談窓口を設置し、相談者のプライバシー保護と不利益取扱い禁止を徹底する義務があります。
相談窓口の設置形態として、人事部内担当者、外部カウンセラー、顧問弁護士、社外専門機関との契約などがあり、企業規模や予算に応じて選択できます。
相談方法は面談、電話、メール、匿名投稿箱、オンライン相談フォームなど多様化を図り、相談者が利用しやすい環境を整備することが大切です。
プライバシー保護措置として、秘密保持義務の徹底、相談記録の厳重管理、関係者以外への情報開示禁止を確実に実施する必要があります。
また、相談を理由とした降格・解雇の禁止、相談者への報復行為の防止など不利益取扱い禁止も重要な要素です。
相談窓口の存在と利用方法を定期的に周知し、相談担当者には専門研修を実施することで、適切な対応力を向上させることが求められます。
対策(3)ハラスメント発生後の迅速で適切な対応
ハラスメント事案が発生した場合、企業は事実関係の迅速な調査、適切な措置の実施、再発防止策の策定を行う法的義務があります。
調査プロセスにおいては、相談を受け付けたら可能な限り速やか(目安として1週間以内)に調査を開始し、関係者へのヒアリングや客観的な証拠の確保を、プライバシーに配慮しながら組織的に進めることが必要です。
措置の具体例として、加害者への指導・研修、配置転換、懲戒処分、被害者への配慮措置として配置変更や休暇取得支援などがあります。
再発防止策では原因分析の実施、職場環境の改善、研修内容の見直し、定期的なフォローアップを継続的に行うことが重要です。
対応期限の目安として、初期対応1週間以内、調査完了1か月以内、措置実施2週間以内に設定し、迅速な解決を図ることが求められます。
対応フローを文書化して関係部署で共有し、外部専門家との連携体制を事前に構築することで、重大事案への対応力を向上させることができます。
適切な事後対応は被害の拡大防止と企業の法的責任軽減につながる重要な取り組みです。
対策(4)業務分担の見直しなど職場環境の改善
より根本的な対策として、企業には、妊娠・出産をきっかけとした個別の業務調整にとどまらず、マタハラが生まれる土壌そのものである「構造的な問題」を解消していく努力が求められます。
業務分担の見直しでは、業務の標準化・マニュアル化、チーム制の導入、代替要員の確保、業務量の平準化により、特定の個人に負担が集中しない体制を構築することが重要です。
勤務制度の柔軟化として、時短勤務、フレックスタイム、在宅勤務、時差出勤の導入により、妊娠中や育児中の社員が働きやすい環境を整備します。
職場風土の改善では、多様な働き方への理解促進、成果主義の導入、長時間労働の是正を通じて、生産性重視の職場文化を醸成することが効果的です。
設備面の配慮として、休憩室の整備、妊婦専用駐車場の設置、重量物運搬の機械化など、物理的な環境改善も必要です。
定期的に匿名の職場環境アンケートなどを実施し、特に妊娠・育児中の社員から「本当は困っていること」の声を吸い上げる仕組みがあれば、より実態に即した継続的な改善が可能になります。
他社の優良事例を参考に、段階的な改善計画を策定することが持続可能な取り組みにつながります。
マタハラ被害にあった時の相談先と対処法


この章では、マタハラ被害にあった時の相談先と対処法について紹介します。
マタハラ被害への対処には主に以下の4つが挙げられます。
- 言動の記録など証拠を確保する方法と重要性
- 会社の相談窓口や労働組合への相談手順
- 都道府県労働局への相談方法(無料・匿名可能)
- 弁護士に相談し法的措置を検討する流れ
対処法(1)言動の記録など証拠を確保する方法
残念ながら、マタハラの被害を訴えても「そんなつもりはなかった」「あなたの勘違いでは?」などと言いくるめられてしまうことも少なくありません。
だからこそ、あなたの主張を「事実」として裏付ける客観的な証拠を、日頃から記録しておくことが、自分を守る最大の武器になります。
記録すべき内容として、発生日時、場所、加害者名、発言内容を可能な限り正確に記録し、同席者の有無や自分の対応も含めて詳細にメモを残すことが重要です。
証拠の種類として、業務日誌や手帳への記録、スマートフォンのメモ機能、録音データ、メールやLINEのスクリーンショットなどがあります。
録音については、相手の同意なく録音しても民事上は証拠能力がありますが、可能であれば事前告知が望ましいとされています。
第三者証言として、同僚の証言、産業医の面談記録、上司との面談メモも有効な証拠となるのです。
被害を受けた直後から継続的に記録を取り、クラウドストレージなど複数の場所に保存することで、証拠の紛失や改ざんを防ぐことができます。
企業の人事担当者は、社員が適切に証拠保全できるよう記録方法をガイドラインで示し、相談時のサポート体制を整備することが求められます。
対処法(2)会社の相談窓口や労働組合に相談する
被害に遭ってしまったら、一人で抱え込まず、まずは社内の相談窓口や労働組合に相談することから始めましょう。
問題を大きくせずに、比較的穏便な形で早期解決を目指せる、最も身近な第一歩です。
相談を受けた会社側には、誠実に対応する義務があります。
相談窓口の種類として、人事部、ハラスメント相談室、産業医、外部EAP(従業員支援プログラム)などがあり、企業規模や体制に応じて選択可能。
労働組合の活用では、団体交渉権の行使が可能で、組合員でなくても相談可能な場合が多くあります。
相談時の準備として、証拠資料の整理、相談内容の要点整理、希望する解決方法の明確化を事前に行うことで、効果的な相談ができるのです。
企業には相談の受付、迅速な調査、適切な措置の実施、プライバシー保護の義務があり、相談者への不利益取扱いは法的に禁止されています。
相談前に企業の相談制度や労働組合の存在を確認し、匿名相談が可能かも事前に調査することが重要です。
企業は相談窓口の周知徹底と相談担当者への専門研修実施により、実効性のある制度運用を図る必要があります。
対処法(3)都道府県労働局へ相談する(無料・匿名可)
社内に相談しても改善が見られない、あるいは相談しづらい場合の、非常に頼りになる味方が、各都道府県の労働局にある「雇用環境・均等室」です。
ここは、無料で、しかも匿名でも相談できる公的な機関。
必要であれば、会社に対して直接指導や解決に向けた話し合いの仲介も行ってくれます。
相談方法として電話、来所、オンライン相談(一部地域)があり、匿名での相談も受け付けているため、社内での解決が困難な場合でも安心して利用できますよ。
労働局の対応として、助言・指導、企業との調整、是正勧告、企業名公表(重大事案)などがあり、中立的で専門的な第三者機関として企業側も真剣に対応せざるを得なくなるのです。
相談時の持参物として、証拠資料、就業規則、雇用契約書、給与明細などを用意することで、より具体的な助言を受けることができます。
解決事例として、企業への指導により配置転換が撤回されたケースや、謝罪と再発防止策の実施が行われた事例があります。
社内相談で解決しない場合は速やかに労働局に相談し、企業への働きかけを依頼することが効果的です。
企業側としては、労働局からの指導を重く受け止め、迅速かつ誠実に対応することが、行政処分や企業名公表といった、より深刻な事態を避けるために不可欠です。
対処法(4)弁護士に相談し法的措置を検討する
深刻なマタハラ被害や他の方法で解決しない場合は、労働問題専門の弁護士に相談し、損害賠償請求や労働審判などの法的措置を検討することが有効です。
法的措置の種類として、損害賠償請求、労働審判、民事訴訟、刑事告発(悪質な場合)があり、被害の程度や状況に応じて選択できます。
損害の種類には精神的損害(慰謝料)、経済的損害(減収分)、治療費などがあり、適切な賠償を求めることが可能です。
弁護士費用として、初回相談30分5,000円程度、着手金20~30万円、成功報酬10~20%が一般的な目安とされています。
解決事例として、300万円の慰謝料認定、原職復帰命令、企業の謝罪広告などの判決が出されており、個人の救済だけでなく社会的な抑止効果も期待できます。
証拠が十分に揃い他の解決方法が困難な場合は、労働問題に精通した弁護士への相談を検討することが重要です。
企業は法的リスクを軽減するため、早期の問題解決と再発防止策の徹底により、訴訟リスクを最小化することが求められます。
同僚の不満?逆マタハラの問題点とは


妊娠・出産への配慮が進む一方で、そのしわ寄せが他の従業員に向かい、新たな不満や対立を生んでしまう「逆マタハラ」の問題が注目されています。
これは個人の問題ではなく、誰もが働きやすい環境を作る上で避けては通れない、組織全体の課題です。ここでは、その原因と根本的な解決策を探ります。
- 逆マタハラの意味と職場で発生する具体的な原因
- 「不公平だ」と感じる同僚の心理的背景と構造
- 属人化を防ぐ業務体制の見直しによる根本的解決策
逆マタハラ(1)逆マタハラの意味と発生する原因
逆マタハラとは、法律で直接的に定義されたハラスメントではありません。
ただし、妊娠・育児中の社員をサポートする会社の仕組みが不十分なために、周囲の社員に過度な業務負担が集中し、結果として「なぜあの人ばかり」「自分たちが損をしている」といった不公平感や、時には嫌がらせにまで発展してしまう、という職場の構造的な問題を指す言葉です。
マタハラとは妊娠・出産・育児を理由とする嫌がらせですが、逆マタハラはその対策により新たに発生する問題として近年注目されているのです。
発生する嫌がらせの例として「独身だから残業して当然」「子どもがいない人は楽でいいね」「私たちばかり負担が増える」といった発言や態度があります。
業務負荷の偏りとして、妊娠中の社員の業務を他の社員が代替することで残業や休日出勤が増加し、新たな責任が押し付けられるケースが見られます。
制度設計の問題として、時短勤務者のフォロー体制不備、代替要員の未確保、評価制度の不平等感が背景にあります。
組織風土の課題として、相互支援の意識不足や多様な働き方への理解不足も要因です。
企業は逆マタハラの定義と問題点を管理職研修で説明し、妊娠・育児支援と職場全体の公平性確保を両立させる施策を検討することが重要です。
逆マタハラ(2)「不公平だ」と感じる同僚の心理
逆マタハラの背景には、業務負荷の不平等、評価制度の不透明さ、キャリア形成への不安などが複合的に作用し、同僚の不満や疎外感を生み出しています。
業務負荷への不満として、「私の仕事量が2倍になった」「いつも私が残業している」「休日出勤は独身者ばかり」といった声が上がることがあります。
評価への不安では「時短勤務の人と同じ評価なのか」「頑張っても認められない」「昇進機会が減った」という懸念が生じることもあるでしょう。
将来への不安として「結婚・出産したら私も迷惑をかけるのか」「独身でいることが悪いのか」という心理的負担も発生します。
孤立感として「チームから取り残された」「相談相手がいない」「配慮されるのは妊娠・育児中の人だけ」という疎外感を抱く従業員もいます。
これらの心理的背景を理解せずに放置すると、職場全体のモチベーション低下や離職率の増加につながる可能性があるのです。
管理職は個別面談で負担感や不安を聞き取り、適切な配慮と説明を行うことが必要です。
企業は多様な働き方を支える制度設計と、全従業員が公平に評価される仕組みづくりに取り組むことが求められます。
逆マタハラ(3)属人化を防ぐ業務体制の見直しが鍵
この根深い逆マタハラの問題を解決する鍵は、特定の「エース社員」に頼りすぎる業務のあり方を見直し、「誰かが休んでもチームで当たり前にカバーできる」業務体制を築くこと。
そして、勤務時間や場所ではなく、成果や貢献度で正当に評価される公平な仕組みを作ることです。
業務標準化の推進として、マニュアル整備、業務フローの見える化、スキルの共有化、クロストレーニングの実施により、特定の個人に依存しない組織体制を構築することが重要です。
チーム制の導入では、複数人での業務分担、相互バックアップ体制、ローテーション制度により、負荷の分散を図ることができます。
代替要員の確保として、派遣社員の活用、業務委託の検討、繁忙期対応の人員計画を事前に整備することで、急な業務変更にも対応可能になります。
評価制度の見直しでは、成果主義の導入、労働時間ではなく貢献度での評価、チーム成果の重視により、働き方の多様性を認める仕組みを作ることが効果的です。
これらの取り組みにより、妊娠・育児中の社員も安心して働き続けることができ、同僚も過度な負担を感じることなく業務に取り組める職場環境が実現できます。
段階的な業務改革により、従業員全員が多様な働き方を理解し、相互支援する企業文化の醸成に継続的に取り組むことが、持続可能なダイバーシティ推進の鍵となります。
まとめ


本記事では「マタハラとは何か」を、厚生労働省の定義や法律、具体的な言動の例を交えてわかりやすく解説しました。
もしあなたが妊娠をしてマタハラの被害に遭われたら、決して一人で抱え込まないでください。
嫌がらせなどの言動の記録を証拠として確保した上で、社内外の相談窓口や労働局に相談することが解決への第一歩です。
企業側は、防止措置を徹底する法的義務があります。
対策が不十分な場合は、改善に取り組むことが重要です。
男性の育休や逆マタハラの問題にもきちんと理解をした上で向き合い、全ての従業員が安心して働ける職場環境を築いていきましょう。



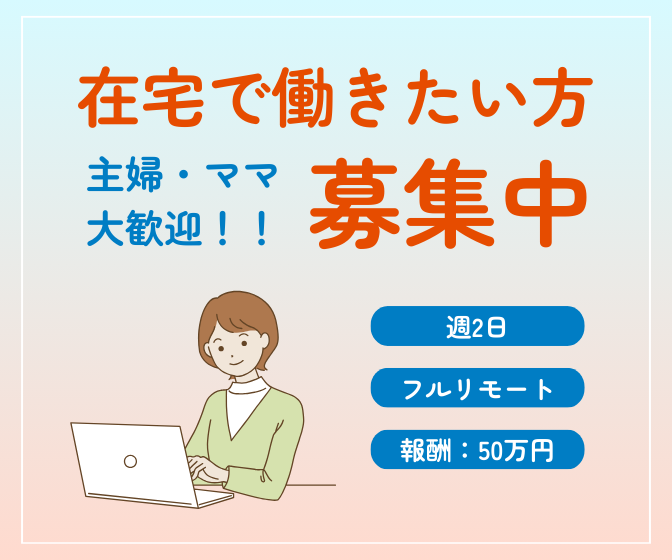

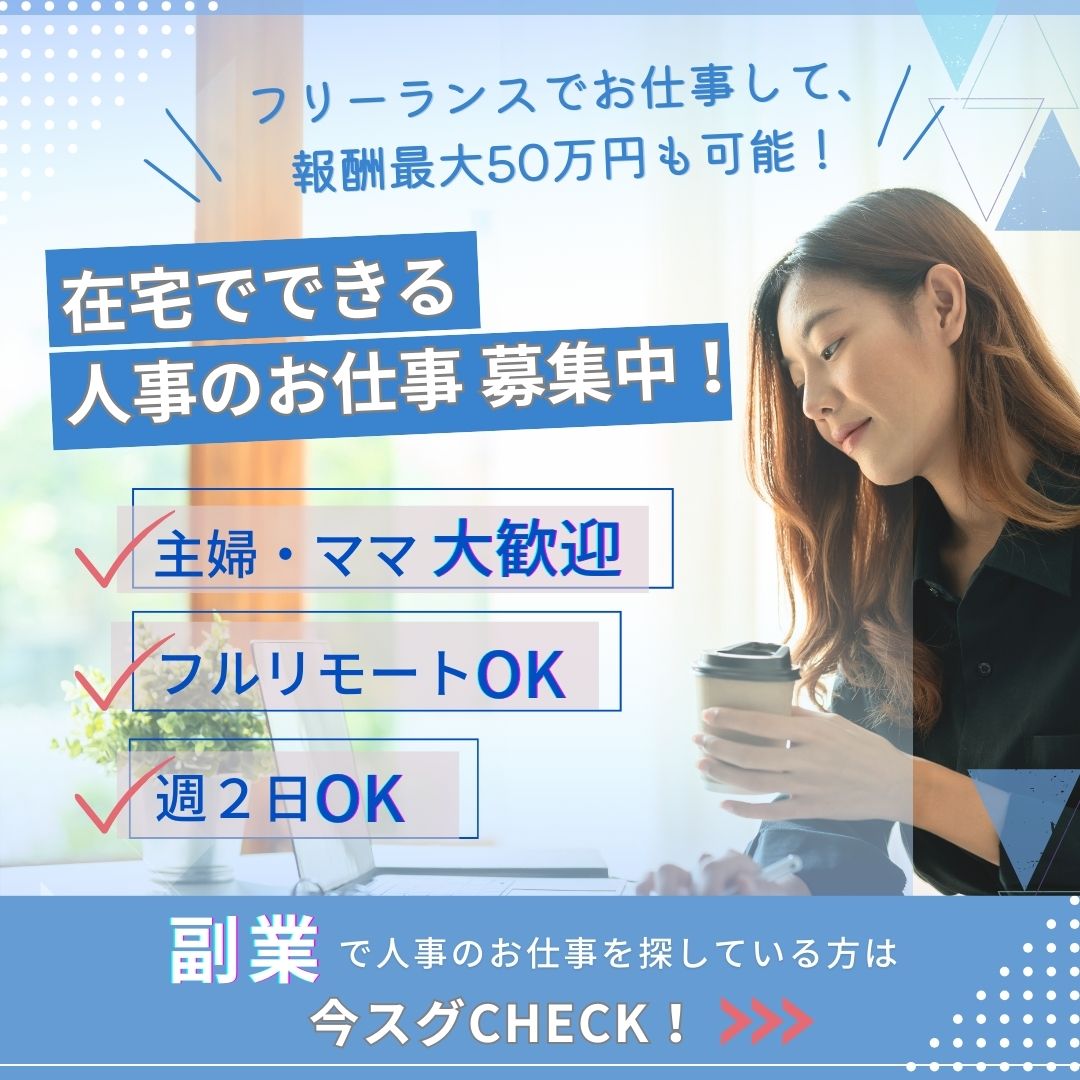

コメント