- フリーランスは原則、雇用保険に加入できません。しかし、副業で一定の条件を満たせば加入できる場合がある。
- フリーランスになっても再就職手当を受け取れます。ただし、条件を満たす必要がある。
- フリーランスが雇用保険の代わりに加入できる、様々なセーフティネットが存在します。
「フリーランスになると雇用保険はどうなるの?」
「会社員を辞めたら、失業給付や再就職手当は受け取れない?」

そんな不安を抱えていませんか?
安定した収入や保障がないフリーランスにとって、万が一のリスクに備えることは大切です。
実際、フリーランスは基本的に雇用保険に加入できませんが、副業で一定の条件を満たせば加入できる場合もあります。
また、雇用保険の代わりに利用できるお得な補償制度や、リスクを軽減するための選択肢もあるんです。
この記事では、雇用保険の仕組みや加入条件やフリーランスになるときの雇用保険の注意点、雇用保険の代わりになる制度をわかりやすく解説します。
フリーランスとして安心して働くためのヒントが得られますよ。
フリーランスは雇用保険に加入できる?


フリーランスとして働くことを考える際、雇用保険に加入できるかどうかは非常に気になります。
雇用保険は、失業時の支えとなる制度ですが、フリーランスの場合、基本的に加入が難しいのが現状です。
ここでは、雇用保険の基本的な仕組みから、フリーランスが加入できるかどうかの判断基準、そして加入できる例外的なケースまでをわかりやすく解説していきます。
- 雇用保険の仕組みと加入条件
- フリーランスは基本的には加入できない
- フリーランスでも雇用保険に加入できるケース
雇用保険の仕組みと加入条件
フリーランスは、原則として雇用保険に加入することはできません。
雇用保険は、会社などに雇われている労働者が、失業した際に生活の安定を図るための制度です。
雇用保険の仕組みと加入条件について、まず結論として、雇用保険は失業時の生活を支えるセーフティネットとして機能し、近年注目されるフリーランス雇用保険の導入も含め、さまざまな働き方に応じた保障の必要性が高まっています。
雇用保険が企業に雇用されている労働者を対象としているのは、事業主が保険料を負担し、労働者が失業した場合に給付金を支給する仕組みだからです。
なぜなら雇用保険は会社員が失業した際の収入源を確保するだけでなく、再就職の支援や職業訓練など多角的なサポートを行う一方、雇用されずに働く人々にも同様の保障を求める声が増加しているからです。
労働者の条件は以下のとおりです。
具体的には、短期や単発のプロジェクトに携わるフリーランスは収入が不安定になりやすいため、失業時の援助を得られる保険制度があれば安心してプロジェクトに取り組めるでしょう。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
これらの条件を満たす従業員は、失業時に給付を受けられるだけでなく、職業訓練や再就職支援といった手厚いサポートも受けられます。
また、会社勤務からフリーランスに転向する人が増える場面では、雇用保険の仕組みと同様の保障があればスムーズに働き方を変えられます。
一方、フリーランスは、企業と雇用契約を結ばずに、業務委託契約などで仕事を請け負う働き方です。
つまり、企業に雇われていないため、雇用保険の加入条件を満たさず、被保険者にはなれません。
最後に、こうした社会的背景を踏まえると、雇用保険の制度や加入条件を理解するとともに、フリーランス雇用保険など新たな保障制度を検討し、多様な働き方を支えるセーフティネットを拡充していくことが不可欠です。



フリーランスは雇用保険の枠組みから外れてしまうため、自身でリスク管理を行う必要があります。
フリーランスは基本的には加入できない
フリーランスは、基本的には雇用保険に加入することができません。
この点は、フリーランスとして活動する上で、しっかりと理解しておくべき重要なポイントです。
フリーランスは基本的に雇用保険に加入できず、フリーランス雇用保険のような別途の仕組みが求められています。
なぜなら雇用保険は雇用契約を前提に設計されており、業務委託や個人事業主として働くフリーランスは法律上の要件を満たせない場合が多いからです。
雇用保険は、あくまで「労働者」を対象とした制度であり、企業と雇用契約を結び、使用者から賃金を得ていることが加入の前提条件となっています。
一方、フリーランスの多くは、企業と業務委託契約や請負契約を結び、独立した事業者として業務を行います。
業務委託契約や請負契約は、雇用契約とは異なり、労働基準法などで定義される「労働者」には該当しないと判断されます。
このため、フリーランスは雇用保険の加入条件を満たしておらず、雇用保険の適用範囲外となってしまうのです。
例えば、会社員からフリーランスに転身したとき、収入の安定性や失業時の保障が心配になる場面で、独自の保険制度があれば安心して働くことができるでしょう。
雇用保険に頼れない分、万が一に備えた貯蓄や、民間の保険への加入などを検討しておくことが重要です。
したがって、現行制度がカバーしきれないフリーランスをサポートするためには、フリーランス雇用保険の導入や新たな制度設計が重要だといえます。
フリーランスでも雇用保険に加入できるケース
フリーランス自身は原則として雇用保険に加入できませんが、例外的に加入できるケース、または従業員を雇用保険に加入させる義務が生じるケースがあります。
フリーランスであっても、雇用契約とほぼ同様の働き方をしている場合や、一定の基準を満たす兼業形態などでは雇用保険に加入できるケースが存在し、同時にフリーランス雇用保険のような新たな保障制度の選択肢も注目されています。
まず、フリーランスが副業として企業と雇用契約を結び、労働者として勤務している場合です。
これは、雇用保険が本来「被雇用者」を対象とする制度であるものの、事実上の雇用関係と認められれば適用範囲に含まれる可能性があるためですし、従来の制度で十分にカバーしきれない働き方に対応する取り組みが進められているからです。
フリーランスが副業で雇用保険に加入できるかどうかの条件は以下の通りです。
| 条件 | 説明 |
| 副業先で「労働者」として雇用されていること | 単なる業務委託ではなく、雇用契約に基づき、企業から指揮命令を受けて労務を提供している必要があります。 |
| 1週間の所定労働時間が20時間以上であること | 副業先での労働時間が週20時間以上である必要があります。 |
| 31日以上の雇用見込みがあること | 短期や単発の仕事ではなく、31日以上継続して雇用される見込みがあることが必要です。 |
また、フリーランスが従業員を雇用している場合は、その従業員を雇用保険に加入させる義務が発生します。



したがって、事業主として雇用保険への加入が必要になります。
例えば、フリーランスとして複数のクライアントと契約している一方で、一部の業務については週20時間以上の就業を継続し、雇用契約に近い形態で働くケースや、フリーランス雇用保険を導入する企業との契約を結ぶ場面などが考えられます。
フリーランスであっても、働き方によっては雇用保険の適用を受けられる、または従業員を加入させる義務が生じるケースがあることを覚えておきましょう。
こうしたケースは限定的であるものの、働き方や契約内容を見直すことで雇用保険への加入が可能になる場合があり、さらにフリーランス雇用保険など新たな保険制度への関心の高まりもあって、多様化する働き方を支えるセーフティネットの拡充が今後一層求められるでしょう。
これらの条件に該当するかを判断するには、労働基準法や雇用保険法に基づいた適切な確認が必要です。
不明点があればハローワークに相談することで、正しい対応が可能になります。
フリーランスとしての働き方をより安心なものにするため、条件をしっかり把握しましょう。
フリーランスになる時の雇用保険の注意点
会社員からフリーランスになることを検討している場合、雇用保険に関する注意点を理解しておくことが重要です。
- 失業給付を受けられる条件
- 再就職手当はもらえる?
- 不正受給に気をつけよう
失業給付を受けられる条件
フリーランスを目指す方でも、会社員時代に雇用保険の加入条件を満たしていれば、一定期間、失業給付を受給できる可能性があります。
雇用保険の失業給付は、被保険者期間や就労実績など特定の要件を満たすことで支給され、フリーランス雇用保険においても同様の給付基準が検討されています。
失業給付は、雇用保険の被保険者が失業した際に、生活の安定を図りながら再就職活動を支援するための制度です。
会社員からフリーランスに転身する場合、働き方が変わっても、過去の雇用保険加入期間やその他の受給要件を満たしていれば、失業給付を受けられる可能性があるのです。
これは、失業給付が収入減少に伴う生活の不安を和らげ、再就職活動を後押しするための制度であり、多様な働き方をカバーするフリーランス雇用保険でも、公平な保障を提供する仕組みが求められているからです。
フリーランスになる前に、失業給付を受けられるかどうかの条件は、下記表の通りです。
例えば、正社員からフリーランスに転向して仕事が途切れた場合、生活費の確保が難しくなる場面が想定されますが、フリーランス雇用保険では被保険者期間や実際の就労実績をもとにした給付条件の整備が期待されています。
| 条件 | 詳細 |
| 離職前の一定期間、雇用保険に加入していたこと | 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上必要(特定受給資格者等の場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上の場合も可)。 |
| ハローワークで求職の申し込みを行い、再就職の意思と能力があること | ハローワークに求職の申し込みをし、積極的に就職活動を行い、かつ健康状態や家庭環境などから、すぐに就職できる状態である必要があります。 |
| 離職後、一定の待機期間(原則7日間)が経過していること | 自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加え、給付制限期間(原則2ヶ月または3ヶ月)が設けられています。この期間中は失業給付は支給されません。 |
出典:基本手当について(ハローワークインターネットサービス)
雇用保険の具体的な手続き(ハローワークインターネットサービス)
フリーランスを目指す場合でも、失業給付の受給要件や事業開始のタイミングに注意することで、受給できる可能性があります。
失業給付は、フリーランスとして独立するまでの生活を支える重要なセーフティーネットとなります。
自身の状況を正確に把握し、ハローワークに相談しながら適切に手続きを進めましょう。
特に、受給期間中に事業を開始(開業届の提出など)すると、受給資格を失う可能性があるため、事業開始のタイミングには細心の注意を払う必要があります。
したがって、失業給付を受けられる条件を理解し、必要な実績や加入要件をあらかじめ満たしておくことが重要であり、フリーランス雇用保険の普及や制度整備を促進することで、多様な働き方を支える社会的基盤が強化されるでしょう。
再就職手当はもらえる?
フリーランスを目指す方でも、一定の条件を満たし、適切なタイミングで手続きを行うことで、再就職手当を受給できます。
再就職手当は雇用保険の基本手当を受給中の早期就職を促す制度であり、フリーランス雇用保険においても同様の支援策が検討される可能性があります。
再就職手当は、雇用保険の失業給付を受けている人が、早く安定した仕事に就く、または事業を始めることを応援するために支給されるお金です。
つまり、会社員が転職するだけでなく、フリーランスとして「事業を始める」場合も支給対象となるのです。
この制度の目的は、失業状態にある人が、新しいキャリアへ早期に移行することを支援することにあります。
早期に就職することで失業期間が短くなり、経済的負担や社会的ストレスが軽減されるため、国としても再就職を積極的に支援しているのです。
フリーランスとして再就職手当を受け取るためには、主に以下の表のような条件を満たすことが必要です。
例えば、会社を辞めてフリーランスとして活動を始めた後、雇用保険を受給しながら再就職を検討する場合には再就職手当の適用が視野に入りますし、フリーランス雇用保険が普及すれば、フリーランスの仕事から他の就業形態へ移行するときにも同様のサポートを受けられる可能性があります。
| 条件 | 詳細 |
| 失業給付(基本手当)の受給資格を満たしていること | 再就職手当は、失業給付の受給資格があることが前提条件です。 |
| 待機期間(原則7日間)が経過した後に事業を開始すること | 失業給付の受給開始後、原則7日間の待機期間が経過した後に事業を開始する必要があります。自己都合退職の場合は、給付制限期間(自己都合退職の場合、1~3か月)が終了後に事業を始める必要があります。 |
| 事業開始日の前日までに、失業の認定を受けていること | 事業を開始する前日までの失業状態について、ハローワークで失業の認定を受けている必要があります。 |
| 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること | 再就職手当の支給額は、基本手当の支給残日数によって決まります。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている必要があります。 |
再就職手当の給付額は以下の通りです。
| 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 70% |
| 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 60% |
再就職手当を含む就職支援策は、雇用保険の大きなメリットの一つであり、こうした制度が整備されれば、多様な働き方を柔軟に選択できる社会がますます実現しやすくなるでしょう。
フリーランスを目指す場合も、再就職手当を受給できる可能性がありますが、受給には条件を満たし、開業届の提出タイミングなどに注意する必要があります。
再就職手当は、フリーランスとしての事業開始を経済的に支援する有効な手段となり得るため、制度の内容を正しく理解し、適切に手続きを進めましょう。
不正受給に気をつけよう
雇用保険の不正受給は、発覚した場合に非常に厳しい制裁を受けることになるため、絶対に行うべきではありません。
雇用保険やフリーランス雇用保険を正しく利用するためには、不正受給を防ぐルールを理解し、制度を健全に維持する意識が必要です。
なぜなら、不正受給は、雇用保険制度を支える大切なお金を、ルールを守らずに不正に受け取る、重大なルール違反だからです。
これは、本来受け取るべき人に必要なお金が届かなくなるかもしれないのです。
不正受給は保険制度の財政を圧迫し、適正に利用している加入者の負担を増やす原因となるからですし、フリーランス雇用保険が普及した場合にも給付の公平性を保つための厳正なチェックが欠かせないからです。
さらに、不正受給は、その多くが発覚し、厳しいペナルティが科せられます。
| 制裁内容 | 詳細 |
| 給付の停止 | 不正を行った日以降、失業等給付は一切支給されなくなります。 |
| 返還命令 | 不正に受給した金額の全額を、一括で返還しなければなりません。 |
| 納付命令 | 不正受給額の2倍に相当する額の納付が命じられます。 |
| 3倍返し | 上記の返還と納付を合わせると、不正に受給した金額の3倍を支払うことになります。 |
| 延滞金 | 返還や納付が遅れた場合、延滞金が加算されます。 |
| 財産の差押え | 悪質な場合は、財産が差し押さえられる可能性があります。 |
| 刑事告発(詐欺罪) | 特に悪質な不正受給は詐欺罪として刑事告発され、懲役刑を含む刑罰の対象となる場合もあります。 |
このように、不正受給は非常に厳しい制裁の対象となり、金銭的な負担はもちろん、社会的信用を失うような、あなたの人生に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、働いているにもかかわらず失業状態と偽って申請したり、フリーランス雇用保険の給付を実態以上に請求したりする場面が考えられますが、こうした虚偽申告が発覚すると厳しい返還命令や罰則を伴うリスクがあります。



不正受給は、「どうせばれないだろう」と軽く考えるべきではありません。
ハローワークによる厳格な審査や調査、コンピュータシステムによる管理・照合、税務署などの関係機関との連携、第三者からの通報など、多くの方法で発覚する可能性があります。
雇用保険は、失業者の生活を守るための大切な制度です。
したがって、不正受給に当たる行為やルール違反をしないよう制度の内容を正しく把握し、手続きや申告を慎重に進めることが求められ、フリーランス雇用保険についても不正受給対策を整えることで、公平かつ安定的な制度運営が期待されるでしょう。
制度を正しく理解し、適切に利用するよう心がけましょう。
フリーランス向け!雇用保険の代わりとなる制度


会社員と違い、フリーランスは雇用保険に加入できないため、万が一の事態に備えて、自身でセーフティネットを準備する必要があります。
ここでは、フリーランス向けに、雇用保険の代わりとなる制度を紹介します。
- フリーランス協会「ベネフィットプラン」
- 小規模企業共済
- あんしん財団の補償や福利厚生
- 日本フルハップ公益財団法人のサービス
- 商工会議所の休業補償プラン
フリーランス協会「ベネフィットプラン」
フリーランス協会が提供する「ベネフィットプラン」は、雇用保険に加入できないフリーランスにとって、いざという時の大きな支えとなる、充実した補償・支援制度です。
フリーランス協会が提供する「ベネフィットプラン」は、フリーランスの働き方を総合的にサポートする制度として注目されており、フリーランス雇用保険のようなセーフティネットを補完する存在になり得ます。
業務上の賠償責任、報酬トラブルへの備え、病気やケガによる収入減少リスクへの対応など、フリーランスのために設計されています。
「ベネフィットプラン」は、フリーランスが直面する多様なリスクに対応する各種保険・補償と、充実した福利厚生サービスを組み合わせて、事業継続の安心を提供します。
特に、フリーランスは、就業不能時の所得補償や、取引先との報酬トラブルに対する備えが重要です。
このプランでは、これらのリスクへの対策を含む包括的なサポートを受けることができます。
なぜならフリーランスは企業勤務に比べ社会保障が手薄になりがちですが、ベネフィットプランを利用することで保険や福利厚生サービスを比較的低コストで利用でき、フリーランス雇用保険と組み合わせることで多角的なリスク管理が可能となるからです。
では、「ベネフィットプラン」には具体的にどのようなサービスが含まれているのか、表を使って詳しく見ていきましょう。
自動付帯されるサービスは以下のとおりです。
| サービス名 | 詳細 |
| 賠償責任保険 | 仕事中の事故やミスで、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害賠償責任を負った場合、最大1億円まで補償します。 |
| 報酬トラブル弁護士費用保険「フリーガル」 | 報酬未払いなどのトラブルに対して、弁護士に相談したり、委任したりする際の費用を支援し、問題解決をサポートします。 |
| 福利厚生サービス「WELBOX」 | 健康支援(健康診断、人間ドック費用補助など)、宿泊施設の割引、レジャー・エンタメの優待など、多岐にわたるサービスを利用できます。 |
また、任意で加入できるサービスは、以下のとおりです。
| サービス名 | 詳細 |
| 所得補償保険 | 病気やケガで働けなくなった場合に、最長1年間、収入の一部を補償します。 |
| 団体長期障害所得補償保険 | 病気やケガで長期間(1年以上)働けなくなった場合に、最長で70歳まで所得を補償します。 |
| 傷害総合保険 | 仕事中や日常生活におけるケガを補償します。 |
そのほか、法律相談、税務相談、契約書チェックなどの業務サポート、さらに住まいや金融に関するサービスも提供されています。
例えば、契約案件が途切れた際に医療保険や収入減少をカバーするサービスを活用する場面や、フリーランス雇用保険の検討段階で既存のベネフィットプランを利用し保障を手厚くする方法が考えられます。
これらの充実したサービスを、年会費わずか1万円(月額換算約833円)で利用できるのは、大きな魅力です。
「ベネフィットプラン」は、雇用保険の代わりとして、フリーランスの皆様の事業と生活を守る強力なサポートツールといえるでしょう。
したがってフリーランス協会のベネフィットプランは、フリーランス雇用保険とあわせて働き方の不安を軽減し、より安定した環境を整えるための有効な手段となるため、その特徴をよく理解し、自身のライフスタイルやリスクに合わせて活用することが大切です。
小規模企業共済
小規模企業共済は、フリーランスを含む小規模事業者のための、積み立て型の退職金制度です。
毎月一定の掛金を積み立てることで、将来事業を廃止した際などに、まとまった共済金を受け取ることができます。
小規模企業共済はフリーランスを含む個人事業主の退職金制度として機能し、フリーランス雇用保険が未整備の現状でも将来の資金確保やリスク管理に有効な手段となり得ます。
小規模企業共済は、国が設立した機関である中小企業基盤整備機構が運営しており、安全性が高く、税制上のメリットも大きいため、多くのフリーランスに利用されています。
これは、企業勤務と比べて社会保障が手薄なフリーランスでも、小規模企業共済を利用することで一定の積立を行い、退職や事業廃止時にまとまった資金を受け取れるからです。
小規模企業共済のサービス内容は、以下の表のとおりです。
例えば、長年フリーランスとして活動していた人が引退を考える際、小規模企業共済で積み立てた資金を使えば生活費や新たな挑戦のための資金を確保できるでしょう。
| 加入対象サービス名 | 詳細 |
| 加入対象者 | 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主や会社の役員など。多くのフリーランスが加入できる。 |
| 掛金 | 月額1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で自由に選べる。 |
| 税制優遇 | 掛金は全額が所得控除の対象となるため、節税効果も期待できる |
| 共済金の受取り | 事業を廃止したり、退職したりした際に、それまで納めてきた掛金に応じた共済金を、一括または分割で受け取ることができる。共済金には、「共済金A」、「共済金B」、「準共済金」の3種類があり、どの共済金が受け取れるかは、共済事由によって異なる。 |
| 貸付制度 | 掛金を担保に低金利で事業資金の融資を受けられる |
小規模企業共済は、フリーランスにとって自身の将来の生活を守るための有効な退職金制度であり、雇用保険に加入できないというリスクを補完する、非常に心強い存在です。
加入実績も160万人と多く、多くの自営業者や小規模企業の経営者に支持されているのは、その信頼性の高さを示しています。
フリーランスとして長期的な視点で事業を継続していくためには、小規模企業共済のようなセーフティネットの活用が不可欠といえるでしょう。
将来的にフリーランス雇用保険が導入されても、共済と併用することで多角的なセーフティネットを構築し、より安心して働き続けられる環境が期待されます。
あんしん財団の補償や福利厚生
あんしん財団が提供する「ケガの補償」と「福利厚生サービス」は、業務中はもちろん、業務外のケガまで24時間補償し、さらに健康管理などのサポートも充実しています。
フリーランスにとって非常に心強いセーフティーネットとなります。
あんしん財団が提供する補償や福利厚生は、フリーランスが不足しがちなセーフティネットを補完する重要な手段であり、フリーランス雇用保険とあわせて活用することで、より安心して働ける環境を整備できます。
これらのサービスは、会社員が雇用保険や会社の福利厚生で得られる安心を、フリーランスにも提供してくれる、大きな魅力を持っています。
フリーランスには企業所属者に比べて保険や福利厚生制度が整備されていないことが多く、業務上の事故や病気などのリスクが課題となりがちですが、あんしん財団は災害補償や健康管理支援、さまざまな福利厚生サービスを通じて、こうした負担を軽減しているのです。
あんしん財団のサービス内容は以下のとおりです。
| サービス名 | 詳細 |
| ケガの補償 | 月々わずか2,000円(保険料1,700円)で、仕事中・仕事以外のケガを24時間補償。死亡補償は最高2,000万円(満80歳以上は1,000万円)、入院は1日あたり6,000円、通院・往診も1日目から補償。フリーランスは仕事中にケガした場合に収入が途絶えるリスクが高いため、この補償は非常に心強い。 |
| 福利厚生サービス | 「あんしん財団WELBOX・KENPOS」が自動付帯。健康診断の補助、レジャー施設の優待、自己啓発支援など、多岐にわたるサービスを利用可能。人間ドック受診時の補助金制度も。 |
| その他のサービス | 安全衛生向上のための補助金、無料の視聴覚教材の貸し出し、使用者賠償責任保険制度(1事故あたり3億円、1会員事業所単位10億円)なども提供あり。 |
あんしん財団のサービスは、中小企業の経営者または従業員を対象としています。
ただし一定の要件を満たせば、個人事業主(フリーランス)として加入できる場合もありますので、あんしん財団に確認するとよいでしょう。
注意点は、病気は補償の対象外であるという点です。
例えば、突然のケガや病気で仕事が続けられなくなる場面でも、あんしん財団の補償を受けることで一定のサポートが期待でき、将来的にフリーランス雇用保険が普及した際には、両方を組み合わせることで生活リスクを多角的にカバーすることができます。
あんしん財団の「ケガの補償」と「福利厚生サービス」は、フリーランスが仕事や日常生活で起こりうる、様々なリスクに備えるための、強力なサポートとなります。



特に、ケガのリスクに備えられる点は、雇用保険にはない大きなメリットです。
フリーランスとして働く上で、あんしん財団のサービスは、雇用保険の代わり、あるいは他の制度と組み合わせることで、より安心な環境を整える、有効な選択肢となるでしょう。
したがって、あんしん財団の補償や福利厚生はフリーランスの安定した働き方を支える上で大きな役割を果たし、今後もフリーランス雇用保険とあわせて利用が検討されるでしょう。
日本フルハップ公益財団法人のサービス
日本フルハップ公益財団法人の提供する多岐にわたるサービスは、フリーランスが健康で安全に働くための強力な支援となります。
健康管理支援、ケガの補償、安全衛生支援、福利厚生といった幅広いサポートを提供し、雇用保険が適用されないフリーランスのリスクを軽減します。
日本フルハップ公益財団法人が提供する各種サービスは、フリーランスに不足しがちな補償や福利厚生を得るための有力な選択肢であり、フリーランス雇用保険と合わせて活用することでより安心して働ける体制を整えられます。
日本フルハップのサービス内容は以下のとおりです。
なぜならフリーランスは企業所属者のような社会保障が十分ではないことが多く、業務上の事故や病気に対する補償や健康管理支援が手薄になりがちだからです。
| サービスカテゴリー | サービス名 | 詳細 |
| 健康管理支援 | 人間ドック受診費用助成 | 最大10,000円まで助成 |
| 健康づくりセミナー、医師による健康相談 | フリーランスの健康維持をサポート | |
| 安全衛生支援 | 安全用品、職場環境改善設備の購入・設置費用の一部助成 | 安全な作業環境を整えるための費用を助成 |
| 交通安全用品の購入費用助成 | 通勤や業務移動時の安全対策を支援 | |
| ケガの補償 | 業務上・業務外を問わず24時間、ケガによる通院・入院を初日から補償 | フリーランスは、ケガ補償があれば、万が一のケガの際も安心 |
| 福利厚生サービス | イベント招待、グルメプレゼント、保養施設の宿泊助成、各種割引・優待 | 仕事だけでなく、プライベートも充実させるための、嬉しいサービスが満載。保養施設の宿泊は、1人1泊あたり2,000円の助成あり。 |
| 相談サービス | 法律、税務、労務管理に関する専門家に無料相談窓口 | 専門家に無料で相談できるのは、非常に大きなメリットです。 |
| その他のサービス | スキルアップ研修の受講費用、環境認証取得費用の一部を助成 | フリーランスとしてのスキルアップや、事業の信頼性向上を支援 |
これらのサービスは、月々わずか1,500円の会費で利用できます。
例えば、突然の病気で入院が必要になった際にも、日本フルハップ公益財団法人の給付や福利厚生サービスを利用すれば、経済的な不安を和らげて仕事に復帰しやすくなるでしょう。
日本フルハップのサービスは、フリーランスの健康、安全、そして生活のあらゆる面を、手厚くサポートしてくれます。
特に、健康管理やケガへの備えは、雇用保険ではカバーされない、フリーランス特有のリスクへの対策として有効です。
こうした仕組みは、フリーランス雇用保険が整備されていない現状でリスクに備える上でも有効であり、将来的にフリーランス雇用保険と併用すれば、社会的リスクを多角的に補えるセーフティネットの構築に寄与すると期待されます。
商工会議所の休業補償プラン
商工会議所の「休業補償プラン」は、フリーランスが病気やケガで働けなくなった際の収入減少リスクに備えるための制度です。
雇用保険に加入できないフリーランスにとって、最長1年間の所得補償が受けられるこのプランは、安心して働くための強力な支えとなります。
商工会議所が提供する休業補償プランは、フリーランスが収入を失った際にも一定の保障を受けられる手段であり、フリーランス雇用保険と組み合わせることで安心感を高められます。
なぜなら、企業に所属していないフリーランスは、病気やケガなどで仕事を休まざるを得ない状況になると収入が大幅に減少するリスクが高いからです。
「休業補償プラン」のサービス内容、特徴は以下のとおりです。
| 特徴 | 詳細 |
| 最長1年間の所得補償 | 病気やケガで働けなくなった場合、最長1年間、所得の一部を補償。 |
| 24時間、国内外を問わず補償 | 仕事中・仕事以外の時間、国内・国外を問わず、24時間いつでも補償の対象。 |
| 入院・通院・自宅療養をカバー | 入院中だけでなく、通院や自宅療養中の期間も補償。 |
| 簡便な加入手続き | 医師の診査は原則不要で、加入手続きが簡単。 |
| 団体割引による割安な保険料 | 団体割引が適用され、個別に加入するよりも保険料が割安(割引率は加入する商工会議所によって異なるが、概ね44%〜52%程度)。 |
| 地震等による病気・ケガも補償 | 地震、噴火、津波による病気やケガも補償対象。 |
例えば、フリーランスとして働く人が数週間から数か月間の休業を余儀なくされた場合でも、商工会議所の休業補償プランの給付によって最低限の生活費を確保できるでしょう。
休業補償プランの加入資格は、商工会議所の会員事業所の代表者、従業員、またはその家族が対象です。
つまりフリーランスが加入するには商工会議所の会員になる必要があります。
加入を検討する際には、居住地または事業所の所在地の商工会議所に確認しましょう。
また、経営者自身の備えとしてだけでなく、従業員の福利厚生としても活用できます。
事業主が従業員のために支払う保険料は、必要経費に計上できます。
商工会議所の「休業補償プラン」は、特に収入が不安定なフリーランスにとって、病気やケガで働けなくなった際の経済的な不安を大きく和らげてくれる、非常に魅力的な保険です。
このプランを、雇用保険の代わりとして、あるいは他の保険と組み合わせて活用することで、より安心して仕事に取り組むことができるでしょう。
したがって、商工会議所の休業補償プランは、フリーランスが直面しがちな収入面の不安を和らげる重要な仕組みであり、将来的にフリーランス雇用保険が導入された際にも、両方を活用することで多様なリスクに対応しやすいセーフティネットを構築できると期待されます。
まとめ


この記事では、フリーランスと雇用保険の関係を解説しました。
フリーランスは原則、雇用保険に加入できません。
しかし、特定の条件を満たせば加入できる場合や、会社員時代の加入状況によっては失業給付等を受け取れる可能性もあります。
また、雇用保険の代わりとなる、フリーランス向けの様々な制度も紹介しました。
これらの制度は、フリーランスのリスクに備え、安心して働ける環境づくりをサポートしてくれます。
特に収入が不安定になるフリーランスにとって、万が一に備え、自分に合ったセーフティネットを選ぶことが大切です。
各制度の違いを理解し、自身の働き方に合わせて、上手に活用しましょう。
「フリーランスとして働くことに興味がある」「自分に合った仕事を見つけたい」そんな方は、人事職特化型エージェント「Carry Up Career」にご相談ください。
人事経験豊富なアドバイザーが、あなたの経験や希望に沿った案件を紹介し、フリーランスとしてのキャリアをサポートします。



気になる方は、ぜひ下記のリンクから詳しく見てみてくださいね。
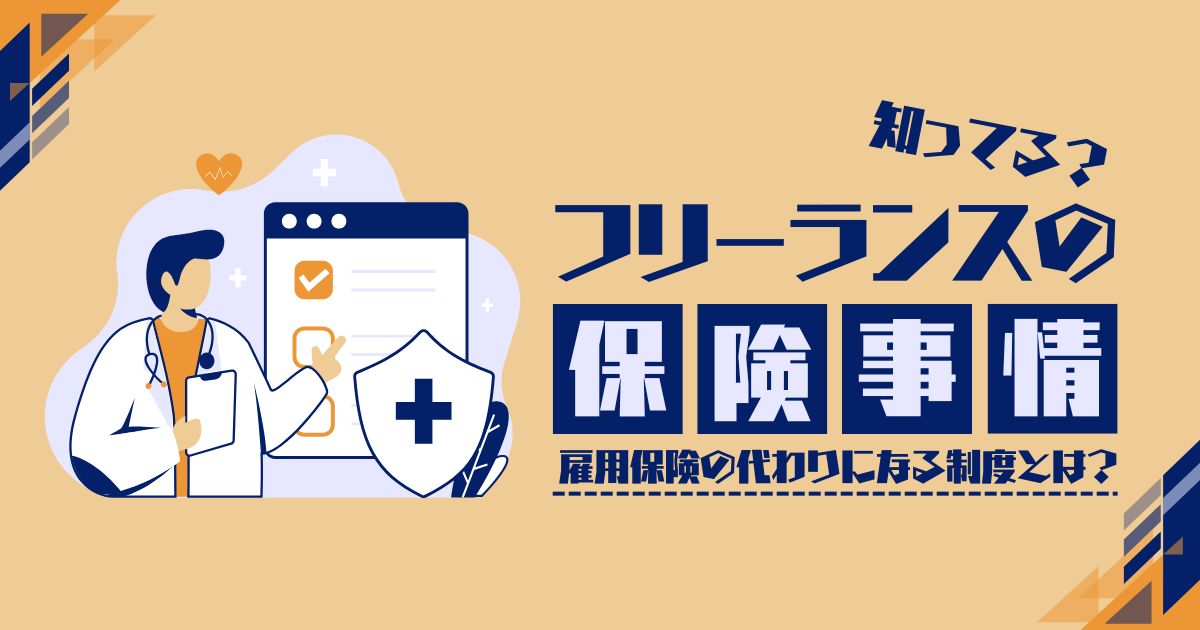
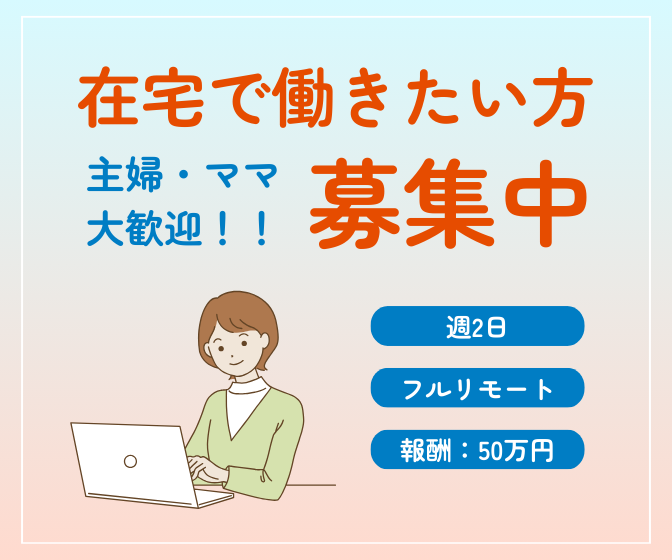



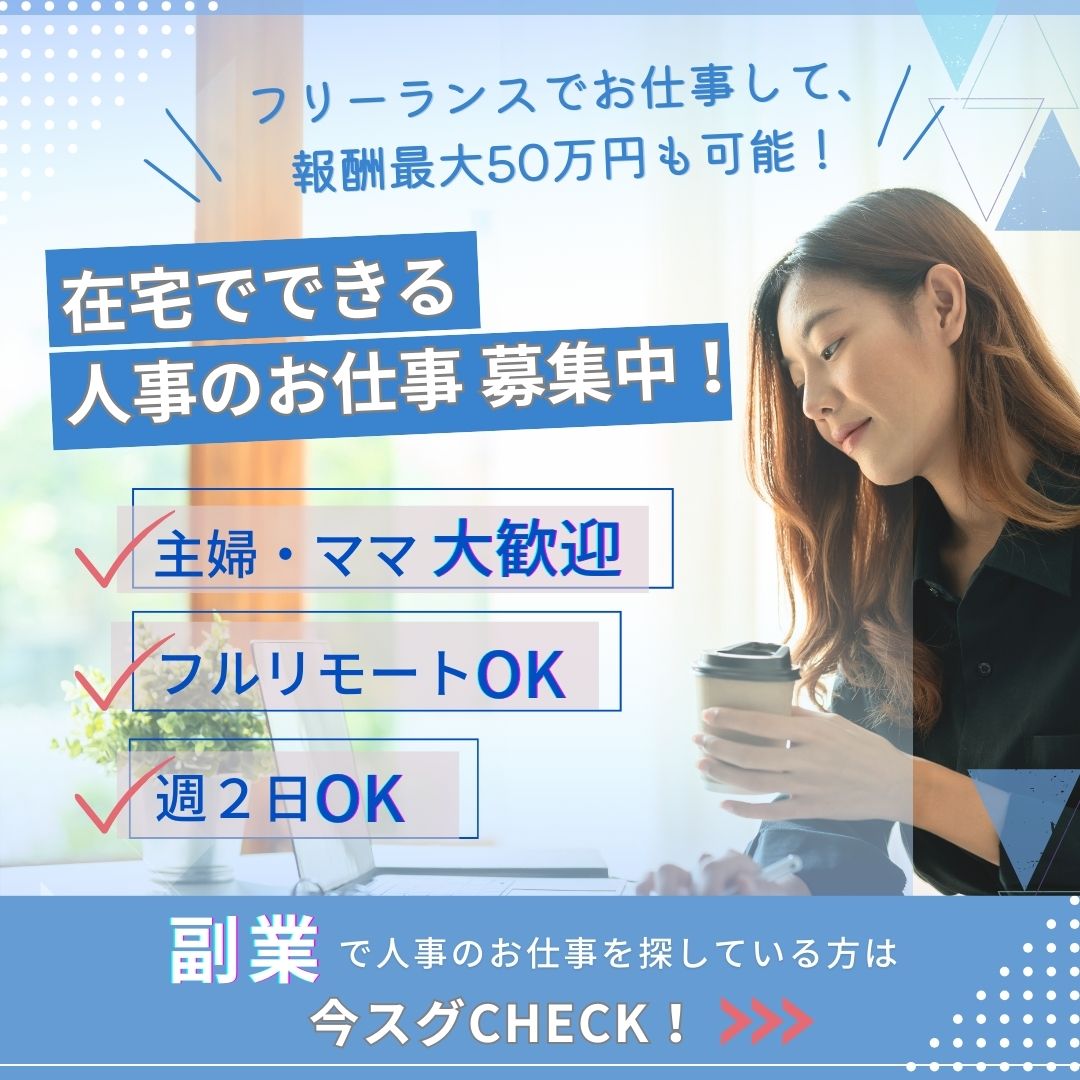

コメント