- エンジニア評価制度は、エンジニアのスキルや貢献を評価し、成長を促す仕組みです。
- 6つの基準を設けることで、公平性を保ち、エンジニア個々のスキルアップや組織の成長を促すことが可能。
- エンジニアの評価は、数値化しづらい部分が多い。創造性や問題解決能力などを適切に評価することが重要です。
「エンジニアとしてのスキルを、人事担当者がどうやって評価すればいいの?」
そんな風に思ったことはありませんか?
実は、その答えのヒントは、多くの企業が導入している「エンジニア評価制度」に隠されているのです。
多くの企業で導入が進むエンジニア評価制度。しかし、その全貌を理解し、エンジニアさん自身のキャリアに活用できている人事は多くありません。
本記事では、エンジニア評価制度と評価基準となる6つのポイントを詳しく解説します。
さらに、評価が難しいと言われる理由や、透明性の高い評価制度を構築するための作成ステップを3段階に分けて、分かりやすく説明します。
これを読めば、自身の強みや弱みを客観的に把握し、次のキャリアステップにつなげることができるでしょう!

今すぐチェックして、理想のキャリアを手に入れましょう!
エンジニア評価制度とは


エンジニア評価制度は、エンジニアのスキルや実績を評価するための明確な仕組みです。
近年、多くの企業で導入が進んでいます。
適切な評価は、エンジニアの成長を促し、モチベーションを高める上で重要な役割を果たします。
企業にとっても、優秀な人材を確保し、組織全体のパフォーマンスを向上させるために欠かせないものです。
エンジニア評価制度が必要とされる理由は、エンジニアの業務内容が多岐にわたり、従来の評価方法では対応することが難しくなっているためです。
技術の進歩が目覚ましい情報技術業界においては、エンジニアは常に新しい技術を学び、変化に対応していくことが必要とされています。
そのため、技術力だけでなく、プロジェクトへの貢献度、問題解決能力、コミュニケーション能力など、多面的な視点から評価することが重要になります。
また、客観的で公平な評価は、エンジニア自身が成長したいという気持ちを高め、将来のキャリアを考える上でも役立つのです。
例えば、サイバーエージェントでは、エンジニア向けに「JBキャリアプログラム」を導入しています。
この制度では、JB1からJB13までの「ジョブグレード」を設定し、各グレードごとに求められるスキルや役割が明確化されています。
また、給与レンジもグレードごとに定められており、半期ごとに評価が見直されます。
「JBキャリアプログラム」は評価制度であると同時に、エンジニアが中長期的なキャリアを考えるための指針としても活用されています。
エンジニア評価制度は、エンジニアの成長と企業の発展、双方にとってメリットのある仕組みです。
適切な評価制度を導入することで、エンジニアは自身の強みや改善点を明確に把握できます。
企業側も、エンジニア一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織全体の競争力を強化することができるのです。



今後も、エンジニア評価制度の重要性はますます高まっていくでしょう。
エンジニア評価制度の6つの評価基準


エンジニア評価制度では、多角的な視点からエンジニアの能力や成果を評価するために、明確な基準を設けることが求められます。
この基準を設けることで、公平性を保ちつつ、エンジニア個々のスキルアップや組織の成長を促すことが可能です。
ここでは、エンジニア評価制度で重要視される以下の6つの評価基準について解説します。
- 技術面やスキル
- プロジェクトの進捗・成果
- 問題解決能力
- マネジメント能力
- コミュニケーション能力
- 語学力
技術面やスキル
技術面やスキルの評価は、エンジニア評価制度の中で最も基本となる評価基準です。
なぜなら、エンジニアの持つ技術的な知識や技能は、仕事の成果やプロジェクトへの貢献度に直結するからです。
そのため、技術面やスキルの評価は、エンジニアのやる気を引き出し、さらに成長を促すことに繋がります。
また、情報技術業界は、日々進化し、新しい技術が次々と登場する業界です。
そのため、エンジニアには、常に学び続け、技術を磨き続けることが求められます。
技術面やスキルの評価を適切に行うことで、エンジニア自身も、自分の強みや弱みを理解し、どの分野を伸ばすべきかが明確になります。
例えば、新しいプログラミング言語の習得は、評価に値します。
技術選定の際に、幅広い選択肢の中から最適なものを選択できるからです。
他にも、セキュリティに関する知識を有していることも評価対象になります。
セキュリティシステムを構築し、機密情報の漏洩や不正アクセスなどのリスクを回避できるからです。
技術やトレンドは常に変化するため、これらの変化に柔軟に対応できることも評価されるエンジニアの特徴です。
つまり、技術面やスキルの評価は、エンジニアの専門性を正しく評価するために重要なのです。
そして、自身の技術レベルを客観的に把握し、市場価値を高めていくためには、継続的にスキルアップを図ることが重要です。
エンジニアとして活躍するために、常に最新技術を学び、自身のスキルを磨き続けましょう。
プロジェクトの進捗・成果
プロジェクトの進捗・成果の評価は、エンジニア評価制度において、非常に大切です。
これは、エンジニアが担当するプロジェクトにおける進捗度合いや成果物が、企業の業績に大きく影響を与えるからです。
期限内に質の高い成果を出すことは、エンジニアに求められる重要なスキルです。
プロジェクトの進捗や成果が重要視されるのは、個人のパフォーマンスだけでなく、チーム全体のパフォーマンスを把握するためでもあります。
予定通りにプロジェクトを進行させ、期待される成果を出すことは、組織としての目標達成に不可欠です。
そのため、企業はプロジェクトに貢献したエンジニアを高く評価するのです。
また、成果に基づいて評価を行うことは、エンジニア自身に責任感を持たせ、より良い成果を出そうという意欲を引き出す効果があります。
例えば、大規模なシステム開発プロジェクトにおいて、担当した機能の開発を予定通りに完了させた場合、これは高く評価されます。
また、開発したシステムが顧客から高い評価を受けた場合、これも大きな成果として認められます。
このように、プロジェクトの進捗・成果を評価することで、エンジニアの実行力や責任感を評価できます。
そして、目標達成に向けて計画的に業務を遂行し、質の高い成果を出すことが、エンジニアとしての市場価値を高めることに繋がります。
プロジェクトの成功に貢献することで、エンジニア自身のキャリアアップにも繋がるのです。
問題解決能力
エンジニア評価制度において、問題解決能力は非常に重要な評価基準です。
問題解決能力が評価基準となる理由は、エンジニアの仕事が、常に「問題解決の連続」だからです。
新しい技術を導入する際、予期せぬ不具合が発生した時、顧客から難しい要望があった時など、エンジニアは日々、様々な問題に直面しています。
これらの問題を、迅速かつ的確に解決する能力は、プロジェクトを成功に導き、会社の利益に貢献する上で、非常に重要です。
例えば、システム障害が発生した際に、ログを分析して原因を特定し、迅速に復旧対応を行うこと、これは評価に値します。
また、顧客からの仕様変更依頼に対して、技術的な実現可能性を検討し、最適な解決策を提案することも重要な能力です。
技術的な問題だけではなく、ヒューマンスキルが必要な場合もあります。
プロジェクト進行において、チーム内の意見対立が起こった際に、双方の意見をくみ取り、建設的な解決策に導くことも問題解決能力があるといえます。
このように、問題解決能力は、エンジニアが現場で直面する様々な課題に、柔軟かつ的確に対応するために必要な能力です。
問題解決能力を高めることは、エンジニアとしての市場価値を向上させるだけでなく、プロジェクトの成功、ひいては企業の成長に貢献することにも繋がります。
自身の市場価値を向上させるためには、普段から、現状に満足せず、常に課題を発見し、その課題に対する解決策を考える癖をつけることが大切です。
マネジメント能力
エンジニア評価制度において、マネジメント能力は、技術力と同じくらい重要視される評価項目です。
これは、プロジェクトを円滑に進め、チーム全体の成果を最大化するために、リーダーシップやマネジメントスキルが不可欠と考えられているからです。
技術に長けていることに加え、リーダーシップを発揮し、チームをまとめる能力が求められています。
例えば、プロジェクトリーダーとして、メンバーの進捗状況を把握し、問題があれば迅速に解決策を講じること。
これは、評価されるべきマネジメント能力の一つです。
また、各メンバーの強みやスキルを理解し、適材適所に配置することで、チーム全体のパフォーマンスを向上させることも、高く評価されるでしょう。
つまり、エンジニア評価制度におけるマネジメント能力とは、技術的なスキルを超えた、チームを率いる力、そして育てる力を指します。
このような能力を持つエンジニアは、組織全体の成長に大きく貢献できます。
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力の評価は、エンジニア評価制度において、非常に大切です。
コミュニケーション能力は、意見を共有し問題を明確化するだけでなく、効果的な意思決定を促し、チーム全体のパフォーマンスを向上させる役割を果たします。
さらに、技術的な内容を分かりやすく説明したり、他部門と調整を行う能力は、エンジニアの専門性を広く活用するために必要不可欠です。
例えば、ミーティングで技術的な課題について説明する際に、専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で説明すること。



これは、高いコミュニケーション能力を示す例です。
また、顧客からの要望を丁寧にヒアリングし、その要望をシステム仕様に落とし込むこと。
これも、評価されるべき能力です。
後輩エンジニアの指導においても、コミュニケーション能力は重要です。
分かりやすい説明や、質問しやすい雰囲気づくりなど、相手の立場に立ったコミュニケーションができるエンジニアは、後進の育成にも貢献できる貴重な人材と言えます。
これらの評価を通じて、エンジニアは自分のコミュニケーション能力の長所や短所を理解し、さらに向上させていくことができるのです。
エンジニア評価制度におけるコミュニケーション能力とは、技術的な知識を効果的に伝え、共有し、相互理解を深めるための能力と言えます。
コミュニケーション能力を磨くことは、エンジニアとしての信頼性を高め、キャリアアップに繋がります。
語学力
エンジニア評価制度において、語学力、特に英語力は、ますます重要な評価基準となっています。
その理由は、IT業界のグローバル化が進展し、海外企業との取引や、外国人エンジニアとの共同プロジェクトが増加しているからです。
そのため、英語で技術的な議論や情報交換ができるエンジニアは、市場価値が高く、企業からも重宝されます。
例えば、海外で開発された新しい技術を学ぶためには、その技術が説明されている外国語の資料を読む力が必要になります。
また、外国の会社と共同でプロジェクトを進める際には、会議やメールなどで、外国語を使って円滑に意思疎通を図る能力が求められます。
さらに、海外の顧客に製品を販売する際には、技術的な説明を外国語で行う必要があるかもしれません。
つまり、語学力は、エンジニアが最新の技術を学び、仕事の幅を広げ、世界で活躍するために、欠かせない能力なのです。
語学力の評価は、エンジニアが世界で活躍し、自身の市場価値を高めるために、非常に重要な取り組みです。
語学力を磨くことは、エンジニアとしての活躍の場を広げ、市場価値を高めることに直結します。
企業も、語学力を持つエンジニアを積極的に評価することで、国際競争力の強化を図ることができるのです。
そのため、自身の市場価値を高めるためにも、普段から英語のニュースや技術書を読むなどして、語学力を磨くことが重要です。
エンジニア評価が難しいと言われる3つの理由
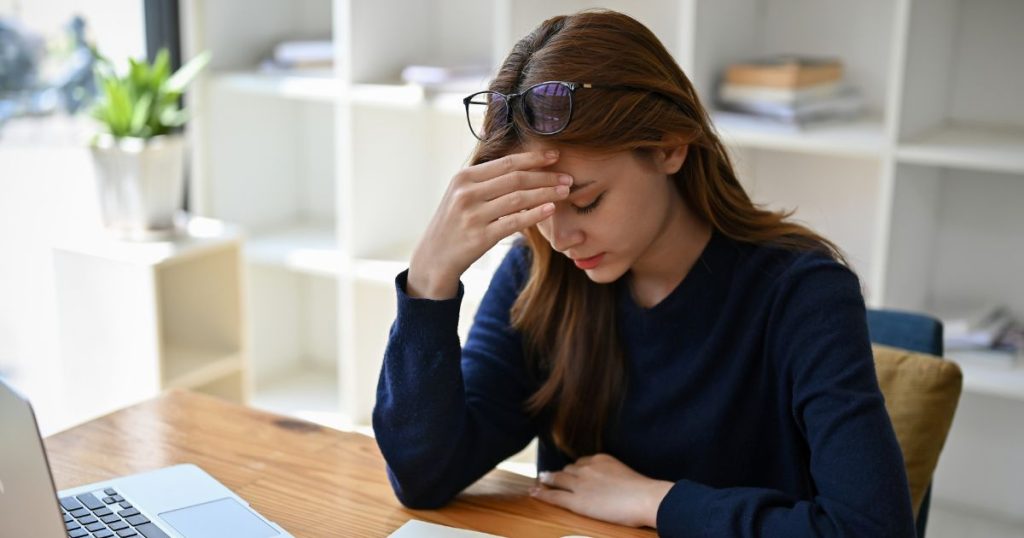
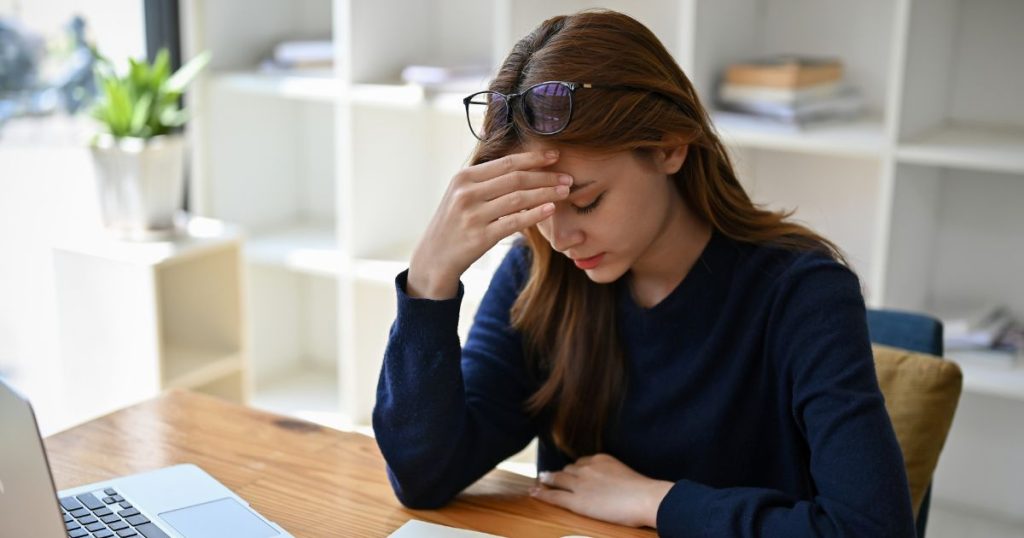
エンジニア評価制度は、多くの企業が導入しているものの、その評価方法が難しいと感じられる理由があります。
ここでは、評価が難しいとされる3つの主な理由について解説します。
- 定量的な評価がしづらい
- 能力やスキルが測りにくい
- 客先常駐の場合は特に評価基準が分かりにくい
定量的な評価がしづらい
エンジニア評価が難しいと言われる理由の一つ目は、定量的な評価がしづらいことです。
特に、創造性や問題解決能力などは、数値化できない成果を測ることが難しい項目です。
しかし、これらの項目は、エンジニアの市場価値や、プロジェクトの成功を評価する上で、重要な指標となるため、企業は適切な評価方法を模索しています。
例えば、新しい技術を積極的に学び、それをプロジェクトに応用することで、開発期間を短縮したり、製品の品質を向上させたりするかもしれません。
しかし、その「新しい技術を学ぶ」という行動自体は、数値化することが難しいです。
また、チーム内で、他のメンバーの意見をまとめたり、技術的な助言をしたりすることで、プロジェクト全体の進行をスムーズにすることもあるでしょう。



これも、数値化しづらい貢献です。
これらの能力や貢献を無視して、数値化しやすい部分だけで評価をしてしまうと、エンジニアの本当の価値を見落としてしまう可能性があります。
これらの能力を評価するためには、具体的な行動や成果を丁寧に観察し、評価する仕組みが必要となります。
エンジニアの業務には、数値化しづらいものの、重要な貢献が多く存在します。
そのため、定量的な評価が難しいのです。
これらを適切に評価するためには、定性的な評価を組み合わせ、多角的に評価することが必要不可欠です。
多面的な評価をすることで、エンジニアの貢献度や成長度合いを、より正確に評価することが可能になります。
能力やスキルが測りにくい
エンジニア評価が難しいと言われる二つ目の理由は、能力やスキルが測りにくいことです。



技術力以外にも、その人の「見えない能力」を評価することは簡単ではありません。
しかし、多角的にエンジニアを評価するためには、数値化できない能力やスキルの評価は避けては通れません。
それゆえ、エンジニアの能力やスキルの適切な評価方法が求められています。
例えば、経験豊富なエンジニアは、過去の経験に基づいて、システム設計上のリスクを事前に察知し、回避策を講じることができます。
しかし、この「リスク察知能力」を数値で表すことは容易ではありません。
他にも、他のメンバーが気づかない問題点を指摘し、より良い解決策を提案することも重要な能力ですが、これも数値化しにくい能力です。
また、若手エンジニアの指導や育成に貢献しているかどうかも、評価が難しい項目です。
能力やスキルが測りにくい場合は、具体的な行動や成果に基づいた評価方法を取り入れることが重要です。
例えば、「経験に基づく判断力」であれば、過去にどのような問題を予見し、どのような対策を講じたのか、その結果どうなったのかを具体的に評価します。
また、「リーダーシップ」であれば、チームメンバーの意見をどのように取り入れたのか、どのように仕事を分担したのか、プロジェクトがどのように成功に導かれたのかを評価します。
このように、具体的な行動や成果に基づいて評価を行うことで、測りにくい能力やスキルも、より正確に評価することができるのです。
その結果、エンジニアは自身の成長を実感し、会社は優秀な人材を確保・育成することができるでしょう。
客先常駐の場合は特に評価基準が分かりにくい
エンジニア評価が難しいと言われる理由の最後、三つ目は、客先常駐の場合は特に評価基準が分かりにくいことです。
客先常駐で働くエンジニアは、自社ではなく顧客先で業務を行うため、上司や人事担当者が直接仕事ぶりを把握することが難しくなります。
そのため、適切な評価が困難になることがあります。
その結果、評価が不透明だとエンジニアのモチベーションが低下し、離職リスクが高まる可能性があります。
客先常駐の場合の評価基準を明確にするためには、客先での仕事ぶりや成果を把握するための仕組みを作ることが重要です。
例えば、定期的に顧客から、エンジニアの働きぶりについて意見をもらうことが考えられます。
また、客先常駐のエンジニアから、月に一度、仕事の状況や成果を報告してもらうことも有効です。
さらに、自社の上司や担当者が、定期的に客先常駐のエンジニアと面談を行い、仕事の状況や悩みなどを詳しく聞くことも大切です。
これらの取り組みを通じて、客先常駐のエンジニアの働きぶりを、より正確に把握し、評価に反映させることができます。
客先常駐という特殊な状況に対応した評価基準を整備することで、エンジニアの努力を正当に評価し、エンジニアの離職を防ぎ、組織全体の安定性を高めることができます。
エンジニア評価制度の作成ステップ


エンジニア評価制度の仕組みを知ることで、自分のスキルや経験が市場でどのように評価されるかを理解でき、キャリア形成に役立てることが可能です。
ここでは、エンジニアが成長し、会社に貢献できるような、エンジニア評価制度の作成ステップについて解説します。
- 評価制度の目的を明確にする
- 評価基準を定める
- 職種に応じた評価項目を作成する
評価制度の目的を明確にする
エンジニア評価制度を作成する上で、評価制度の目的を明確にすることは、評価制度を設計・運用する上での指針となります。
評価制度の目的を明確にすることで、どのような評価項目や評価基準が適切か判断できるからです。
そのため、評価制度を適切に運用する上で、第一に必要なステップとなります。
目的が曖昧なまま評価制度を作ってしまうと、評価の基準が定まらず、評価する人によって結果が変わったり、エンジニアが評価に不満を持ったりする可能性があります。
目的を明確にすることで、評価制度全体に一貫性が生まれ、エンジニアにとっても、評価者にとっても、分かりやすく、納得感のある評価制度を作ることができるのです。
例えば、評価制度の目的が「人材育成」にある場合、スキルアップやキャリア形成を重視した基準を設けることが効果的です。
一方、「業績向上」が目的の場合には、プロジェクトの成果や貢献度に焦点を当てた評価基準を設定する必要があります。
このように目的に応じて評価制度を設計することで、組織の目指す方向性に一致した評価が可能となります。
評価制度の目的を明確にし、それに基づいて基準を設けることは、エンジニア評価制度を構築するための第一歩です。
評価基準を定める
エンジニア評価制度では、具体的かつ公平な評価基準を定めることが、制度の透明性と有効性を高めるために欠かせません。
評価基準が明確であれば、エンジニアが求められる成果やスキルを正確に理解でき、業務目標に集中することができます。
また、基準が不明瞭な場合に生じる誤解や不満を防ぎ、組織全体の信頼感を向上させる効果もあります。
例えば、技術スキルの評価基準として、プログラミング言語ごとの習熟度をレベル分けし、それぞれのレベルに到達するための条件を明確にすることが考えられます。
また、プロジェクトの成果については、達成率や品質、顧客満足度などの指標を用いて、定量的に評価することが考えられます。
また、達成すべき目標をエンジニアごとにカスタマイズし、定期的に進捗を確認することで、個々の成長をサポートできます。
このように、具体的かつ公平な評価基準を定めることで、エンジニア評価制度の透明性と有効性を高めることができます。
評価基準を明確にすることは、エンジニアの成長を促し、組織全体のパフォーマンスを向上させる上で、非常に重要なステップです。
評価基準を定める際には、客観性と具体性を重視することが重要です。
職種に応じた評価項目を作成する
エンジニア評価制度では、職種や専門分野に応じた評価項目を作成することが、個々のスキルと貢献を正確に評価するために欠かせません。
エンジニアリングには、ソフトウェア開発、インフラ管理、データ解析など、多岐にわたる職種が存在し、それぞれ必要とされるスキルや成果が異なります。
一律の評価項目では公平性を保つことが難しく、適切な成長支援やモチベーション向上につながりにくいためです。
そのため、それぞれの職種に特化した評価項目が必要です。
職種に応じた評価項目を作成することで、より公平で納得感のある評価を実現できます。
例えば、ソフトウェア開発エンジニアにはコード品質や開発スピード、チームでのコラボレーションが重要な評価項目となります。
一方で、インフラエンジニアにはシステムの稼働率、トラブル対応の迅速さ、セキュリティ対策の実績が求められます。
このように、エンジニアの職種に応じて、評価項目を細分化し、それぞれの専門性を適切に評価することが重要です。
職種に応じた評価項目を作成することで、エンジニアの多様なスキルや貢献を正しく評価することができます。
その結果、エンジニアのモチベーション向上と、組織全体の成長に繋がるのです。
まとめ


この記事では、「エンジニア評価制度」について詳しく解説しました。エンジニア評価制度は、エンジニアの能力や貢献を適切に評価し、成長を促すための仕組みです。
評価基準には、技術面やスキルだけでなく、プロジェクトの成果、問題解決能力、マネジメント能力、コミュニケーション能力、語学力などがあります。
しかし、エンジニアの評価は、数値化しづらい、能力が測りにくい、客先常駐だと評価がわかりにくいなどの理由で難しいと言われています。
そのため、評価制度を作る際は、目的を明確にし、評価基準を定め、職種に応じた評価項目を作成することが重要です。
に、フリーランスとしての活動を考えている方や、副業を始めたい会社員の方にとって、企業の評価基準を知ることは大きな強みになります。
自分のスキルや経験がどのように評価されるのかを理解すれば、単価交渉や求人選びにおいても自信を持って行動できるでしょう。
キャリアについて相談したいエンジニアの方には、人事職特化型エージェント「Carry Up Career」がおすすめです。
「Carry Up Career」では、プロのアドバイザーがあなたの経験を丁寧にヒアリングし、あなたの強みを最大限に活かせる案件を紹介します。



気になる方は、ぜひ下記のリンクから詳しく見てみてくださいね。



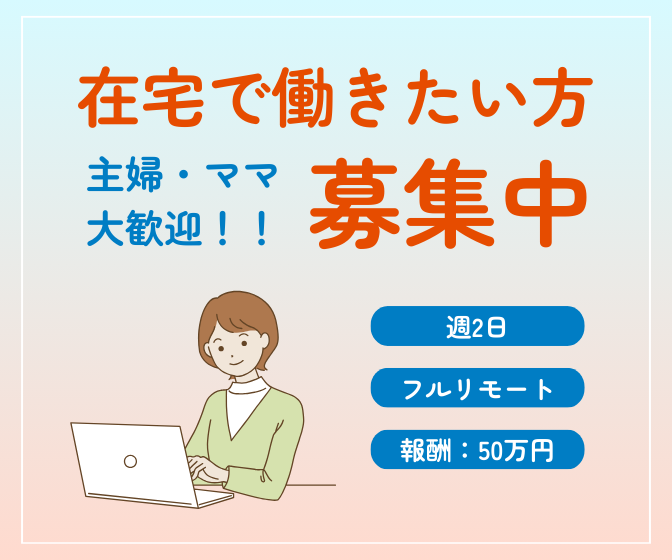

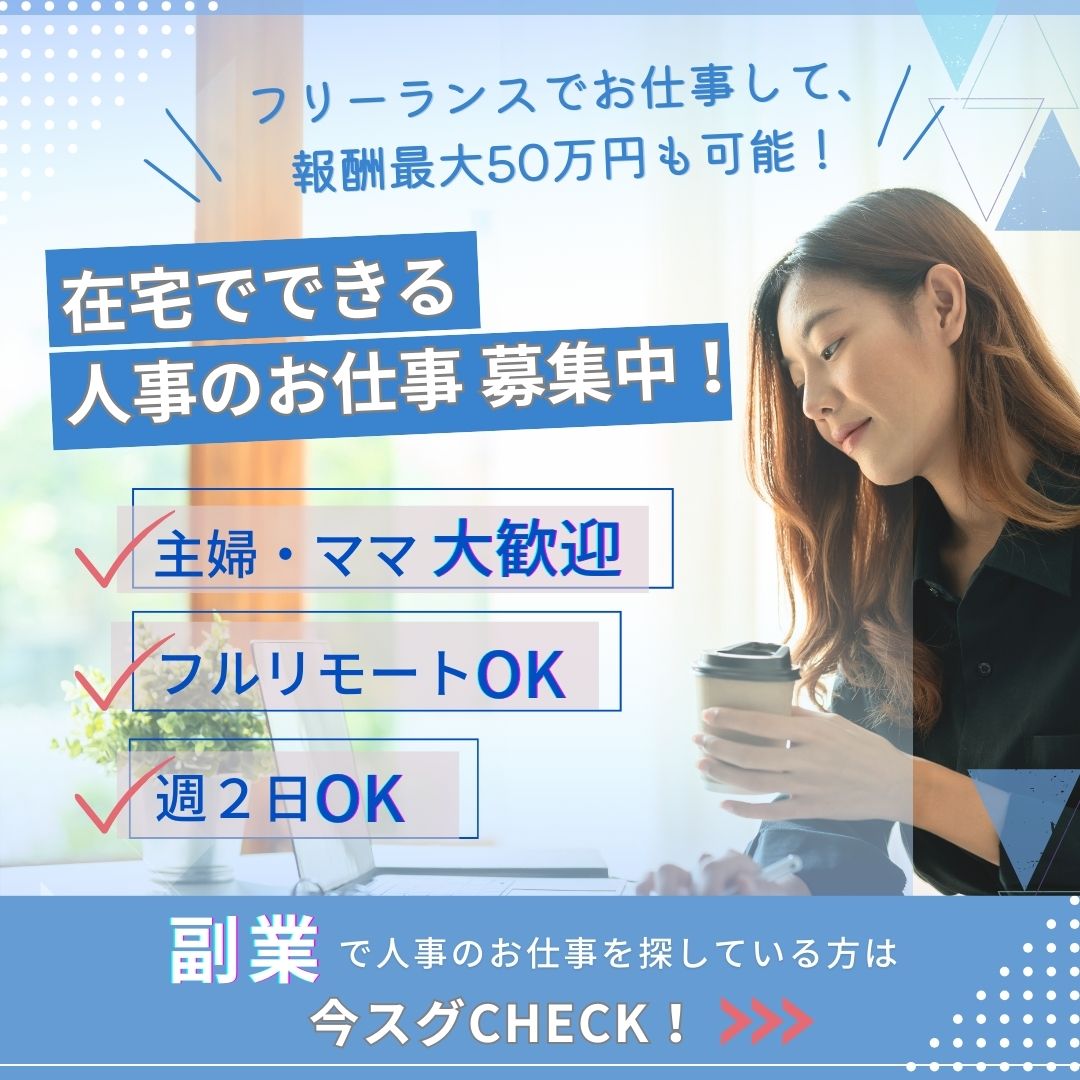

コメント